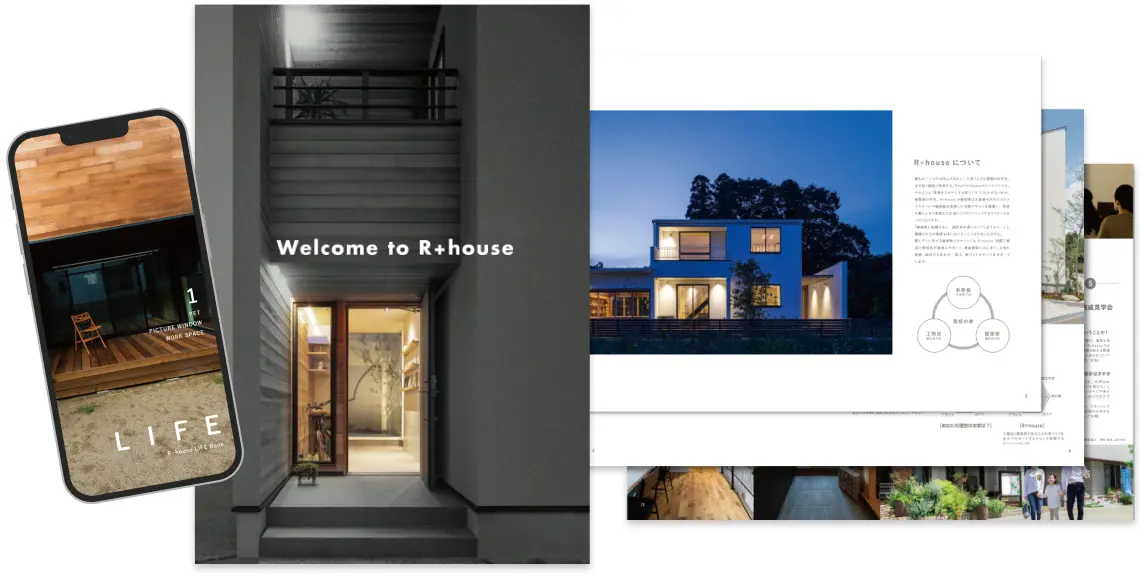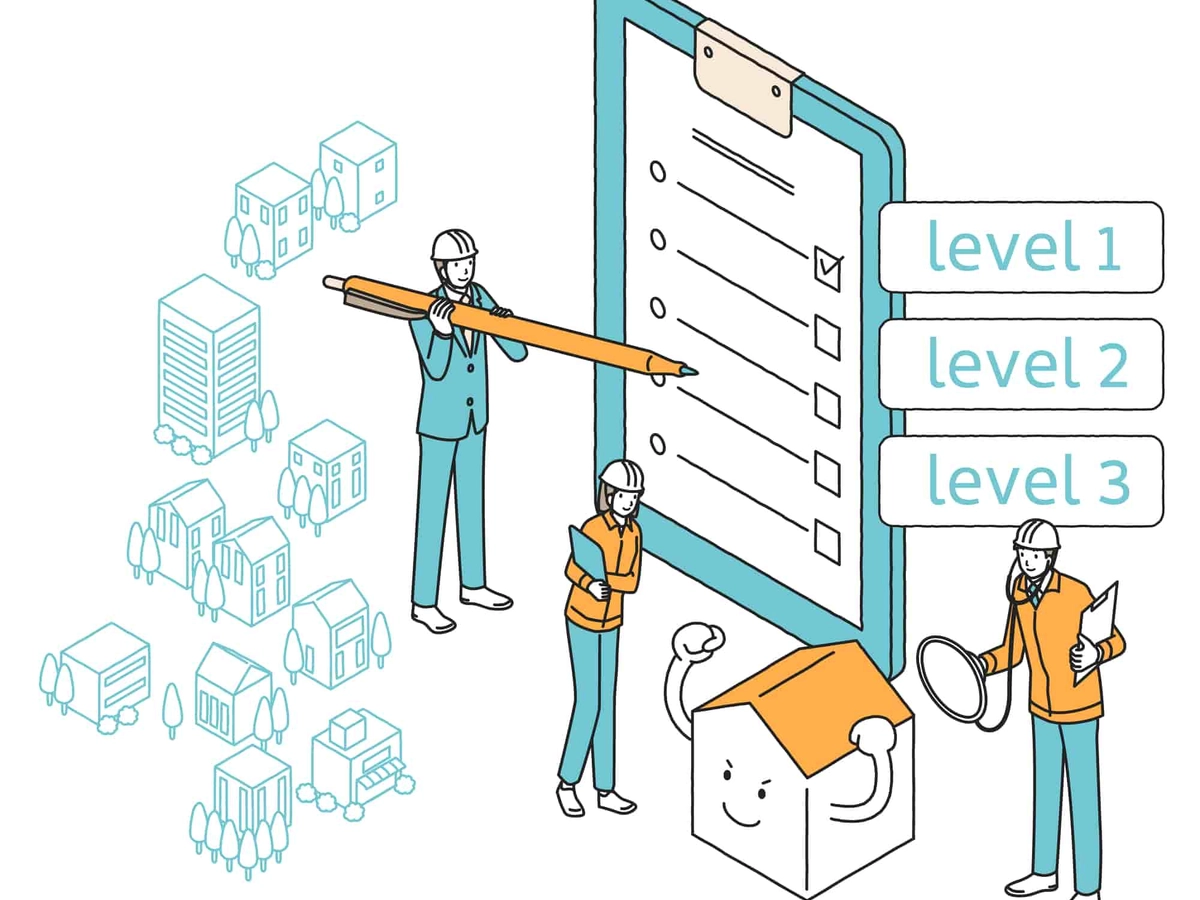耐震等級の基本情報をチェック
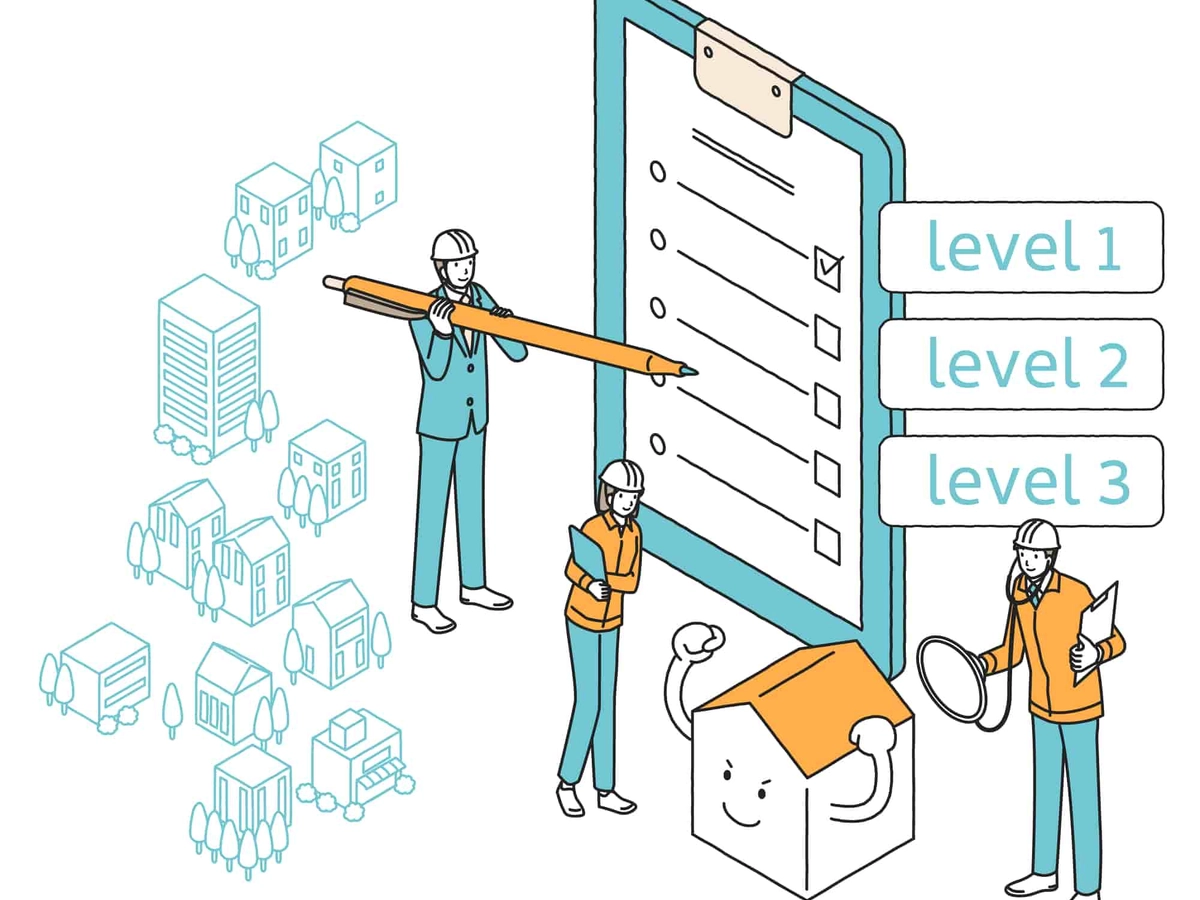 写真②耐震等級1・2・3-min .jpg 87.78 KB
写真②耐震等級1・2・3-min .jpg 87.78 KBまずは、注文住宅を建てるうえで重要な、耐震等級に関する基本情報について解説します。
そもそも耐震等級とは?
耐震等級とは、住宅性能表示制度において、地震への強さを示したものです。住宅性能表示制度は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」のもと、2000年10月から本格的に運用され始めました。
制度の目的は、住宅の性能をわかりやすく表示し、住まいに関するトラブルを未然に防ぐこと。高品質な住宅を取得しやすい市場の形成を目指す制度です。国土交通大臣が定める日本住宅性能表示基準を共通ルールとし、第三者機関による審査を経て評価書を受け取れる仕組みです。
新築住宅における評価項目には、構造の安定や劣化の軽減など10の分野に関する33の性能表示事項があります。その1つ目に挙げられるのが「耐震等級」です。
参考元:国土交通省|新築住宅の住宅性能表示制度ガイド
耐震等級と耐震基準との違い
耐震等級について調べる中で「耐震基準」という言葉を目にしたことがある方もいるでしょう。耐震基準は建築基準法のもと定められており、建物を建てる際に条件を満たす義務があります。
耐震基準は、大きな地震の発生をきっかけに見直しおよび改正が行われてきました。1981年に制定された「新耐震基準」では、震度6強~7相当の地震時に、建物が人命に関わる倒壊などの被害を受けないように定められています。また、2000年には、基礎や接合部の仕様などについて明確な基準が新たに設けられました。
一方、住宅性能表示制度の活用は任意です。家づくりの際に耐震等級を取得する義務はありません。
そのため、耐震等級の認定を受けるかどうかは、お施主様自身で検討可能です。参考元:農林水産省 林野庁|木造住宅の耐震性について
耐震等級1・2・3の違い
耐震等級は1~3の数字で表され、数字が大きいほど高い耐震性を示します。また、耐震等級は構造躯体の倒壊および損傷を防ぐ観点で定められています。ここで、耐震等級1・2・3の違いを見ていきましょう。
| 耐震等級 |
構造躯体の倒壊しにくさ |
構造躯体の損傷しにくさ |
該当する主な建築物 |
| 1 |
震度6強以上の地震で倒壊しない |
震度5強相当の地震で損傷しない |
一般的な住宅 |
| 2 |
震度6強以上の1.25倍の地震で倒壊しない |
震度5強相当の1.25倍の地震で損傷しない |
学校や病院 |
| 3 |
震度6強以上の1.50倍の地震で倒壊しない |
震度5強相当の1.50倍の地震で損傷しない |
警察署や消防署 |
耐震等級1は、耐震基準と同レベルの耐震性を示します。耐震等級2は災害時に避難場所となる公共施設、耐震等級3では防災拠点となる建物をイメージすると、強度の違いがぐっとわかりやすくなるでしょう。
参考元:国土交通省|新築住宅の住宅性能表示制度ガイド
耐震等級を決定づける4つのポイント
 写真③4つのチェックリストを確認する人々-min .jpg 43.72 KB
写真③4つのチェックリストを確認する人々-min .jpg 43.72 KB次に、耐震等級を決めるうえで重要な4つの要素について解説します。
ポイント1|基礎の耐震性
高い耐震性を保つには、建物の土台である基礎に高い強度が必要です。基礎の強度を高めることで、上階に対する地震の揺れによる影響を軽減できるでしょう。
荷重を分散できる方法で基礎を組んだり、適切に鉄筋を配したりすることで、土台の耐震性を高められます。
ポイント2|建物の重さ
建物自体の重さが軽いほど、地震の揺れによる影響は小さくなるといわれています。建物の構造材として木材を選ぶ、また瓦よりも軽い金属屋根を採用するなどし、建物の軽量化を図るのがポイントです。過剰な装飾を控えることも、住宅の軽量化につながります。
建物の強度や住みやすさを考慮しつつ、不要な重量を削減することが大切です。
ポイント3|耐力壁の配置
建物が地震や強風の際、水平方向に働く力に抵抗するために構造上必要な壁を「耐力壁」と呼びます。耐力壁の適切な配置は、地震による影響を家全体にうまく分散するうえで欠かせません。例えば、耐力壁の配置に偏りがある場合、地震による負荷が建物の一部に集中し、ねじれが生じるなどのリスクがあります。
建物の四方に耐力壁をバランス良く配置する他、上下階で設置箇所を揃えるのも有効な手段です。
ポイント4|耐力壁や柱の量
耐震等級3を取得するメリットとは?
 写真②メリットにチェックが入ったクリップボードの紙-min .jpg 82.57 KB
写真②メリットにチェックが入ったクリップボードの紙-min .jpg 82.57 KB
マイホームで耐震等級の取得を考える際、どのレベルまで耐震性を高めておくかは重要です。「耐震等級3まで高める必要はあるの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。ここでは、耐震等級3を取得するメリットについて解説します。
災害時の損害リスクを低減できる
耐震等級3を取得するメリットは、なんといっても災害時における住宅の損害リスクを軽減できる点です。震度7程度の大きな地震の際も、耐震等級3の住宅では、建物が倒壊する可能性は低く、損傷が生じた場合でも住まいの基本的な機能は維持できるといわれています。
国土交通省の発表によると、2016年4月に発生し、震度7の大きな揺れを2度も観測した熊本地震でも、耐震等級3の木造建築物では被害が比較的少なかったとわかりました。具体的には、地震の被害を受けなかった木造建築物は、耐震等級1相当の建物で60.1%、耐震等級3の場合は87.5%でした。また、耐震等級3の木造建築物では、この地震により大破・倒壊した建物は1棟もなかったといいます。
いつ発生するかわからない地震に備えるなら、耐震等級3を取得するに越したことはありません。
参考元:国土交通省 住宅局|「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書のポイント
売却時に高値が付く可能性がある
耐震等級3の住宅は、より高額で売却できる傾向にあります。マイホームを建てた後、なんらかの理由で住宅を売却する可能性はゼロではありません。耐震等級3を取得している住宅は、優れた耐震性能に対する客観的な評価を受けていることから、資産価値が高いと判断されやすいメリットがあります。
立地や間取りなどにより、必ずしも高値が付くとは限らないものの、同条件で比較した場合、耐震等級3の取得が有利に働くでしょう。
コスト面における優遇措置を受けやすい
家づくりの際、耐震等級3を取得することには、コスト面におけるメリットもあります。
住宅ローンの金利優遇
耐震等級2以上を取得している住まいでは、住宅金融機構支援機構が提供する住宅ローン「フラット35」において、適用金利の引き下げが可能です。複数あるフラット35プランの1つ「S」では、耐震等級3の住宅の場合、初めの10年間において金利の引き下げが叶います。毎月のローン返済額を抑えられるのが魅力です。
地震保険の割引率
火災保険に付帯する形で加入可能な地震保険。地震による火災や津波により住宅が損害を受けた際の補償は、火災保険では賄えません。そのため、加入義務はないものの、地震保険は重要な役割を担っています。
地震保険には、耐震等級割引制度があり、等級1で10%、等級2では30%、等級3なら50%も保険料が割引かれます。保険料が気になる場合も、耐震等級3を取得していれば、地震保険の加入を検討しやすくなるでしょう。
参考元:内閣府 防災情報|住まいの地震保険の概要参考元:財務省|地震保険制度の概要
贈与税の非課税限度額の加算
耐震等級3を取得するデメリットはある?
 写真③デメリットにチェックが入ったクリップボードの紙-min .jpg 82.52 KB
写真③デメリットにチェックが入ったクリップボードの紙-min .jpg 82.52 KB
安全面やコスト面において多数のメリットがある耐震等級3。しかし、耐震等級3の取得にはデメリットもあります。詳しく見ていきましょう。
建築費用が高額になる傾向がある
間取りに制限が生じる可能性がある
耐震等級3を取得するには、先述のとおり柱や壁の配置や量が重要なポイントとなります。そのため、窓や柱を自由に配置できない可能性があるでしょう。柱のない大広間や吹き抜けなど、開放的な間取りを希望する場合には注意が必要です。
R+houseネットワークでは、建築家と工務店が協力して、お施主様の理想にかなう間取りをご提案します。吹き抜けや大開口のある開放的な住まいの施工実績も豊富です。
耐震等級3を取得するための具体的な方法と費用
 写真⑥図面上の計算機とお金と住宅模型-min .jpg 90.92 KB
写真⑥図面上の計算機とお金と住宅模型-min .jpg 90.92 KB続いて、耐震等級3を取得する方法や費用について見ていきましょう。
耐震等級3の算出方法
耐震等級を算出する方法は大きくわけて2つあります。1つは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示計算。もう1つが構造計算の一種である「許容応力度計算」です。同じ等級3でも、許容応力度計算を経た住まいのほうが、より強度が高くなります。というのも、許容応力度計算は、基礎や床、屋根、構造材、接合部といったさまざまな部分の強度を総合的に計算するもので、より精密な算出方法であるためです。
南海トラフ地震などによる被災リスクが高い地域で家づくりを検討される方は、許容応力度計算のもと耐震等級3を取得するのが良いでしょう。
耐震等級3の申請・証明書発行の手順
耐震等級の認定を受けるには、以下の手順を踏む必要があります。
・施工会社/設計事務所に耐震等級3を取得する旨を伝える
・施工会社/設計事務所が指定住宅性能評価機関に「設計住宅性能評価」を申請する
・設計住宅性能評価書に基づき施工会社/設計事務所が建設工事を行う
・施工会社/設計事務所が「建設住宅性能評価」を申請する
・評価機関が設計通りに施工されているか検査する
・「建設住宅性能評価書」を証明書とし耐震等級3が認定される
耐震等級3を取得するには、まず設計の段階で性能評価を受けなければなりません。その後、設計どおりの工事が行われているかが検査されます。一般的には基礎配筋工事・躯体工事の完了時や竣工時に検査が行われ、すべての審査に合格することで、住宅性能評価書を取得できるのです。
耐震等級3を取得するのにかかる費用
耐震等級3を取得する際に発生する主なコストは以下の3点です。
・住宅性能評価にかかる費用
・構造計算にかかる費用
・施工にかかる費用
専門機関での住宅性能評価にかかる費用の相場は、約30万円といわれています。加えて構造計算を行う場合にも、30万~100万円ほどの費用が発生します。また、耐震性を高めるため、通常よりも施工費が100万円以上高額になる可能性もあるでしょう。
住宅の規模によってもかかる費用が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
耐震等級3の取得に関する注意点
 写真④家と注意点 (1).jpg 36.37 KB
写真④家と注意点 (1).jpg 36.37 KB
ここからは、耐震等級3を取得するにあたり、注意したい3つのポイントを確認しておきましょう。
・設計前に耐震等級の取得を検討する
・耐震等級3の住宅でも倒壊のリスクはある
・耐震等級3「相当」との違いを把握しておく
耐震等級の認定を受けるには、着工前に設計に関する申請が必要です。認定を受けたいと思っても、着工後では評価を受けられません。そのため、耐震等級3の取得を検討する際は、設計前の段階で施工会社/設計事務所に相談しましょう。
耐震等級3の住宅であっても、地震対策は必要です。家具の固定や非常時の準備は欠かせません。
「耐震等級3相当」という言葉にも注意が必要です。「相当」といわれる場合、実際には評価を受けていない可能性があります。この場合、各種優遇措置の対象とならないため、施工会社/設計事務所に審査の有無をきちんと確認しましょう。
R+houseの家づくりは耐震等級3が標準仕様!
 写真⑧三重県_砂利と土間コンクリートの外構のあるシンプルな家 .jpg 663.51 KB
写真⑧三重県_砂利と土間コンクリートの外構のあるシンプルな家 .jpg 663.51 KB最後にR+houseの家づくりにおける強みを紹介します。R+houseの注文住宅は、耐震等級3が標準仕様です。優れた耐震性と低コストを両立できる理由を以下にまとめました。
・安定性に長けた「べた基礎」
・独自の耐震パネル工法
・専門家による構造チェックR+houseでは、基礎全体で家の荷重を支える「べた基礎」を採用。床下全面をコンクリートで覆うことで、土台から耐震性を高めています。また、床と壁が一体となり「面」で建物を支える耐震パネル工法により、地震の揺れを分散させるだけでなく、横からの強い力にも高い耐性を発揮します。構造体が規格化された工法のため、品質の安定性とコストの削減を実現可能です。
設計時には、構造専門の建築家がさまざまな角度から住宅の強度を厳密に分析。地震や強風に負けない家づくりを叶えます。
耐震等級3の注文住宅を建てるならR+houseネットワークの工務店へ
 写真⑨住宅・不動産について相談する様子-min.jpg 96.29 KB
写真⑨住宅・不動産について相談する様子-min.jpg 96.29 KB
マイホームを建てるにあたり、いつ起きてもおかしくない地震に備えるなら、耐震等級3を取得しておいて損はありません。耐震等級3の取得に要する費用に不安がある方は、コスト面におけるメリット・デメリットを比較したうえで、取得を検討しましょう。
R+houseネットワークの工務店では、資金計画の段階から家づくりをサポート。丁寧なヒアリングを通して、理想の住まいを予算に合わせて提案します。耐震性だけでなく、断熱性・気密性にも優れたおしゃれな高性能住宅を建てたい方は、ぜひお近くのR+houseネットワークの工務店までご相談ください。
>>安心安全に暮らせる、耐震等級3の住まい!R+houseネットワークの性能についてはこちら