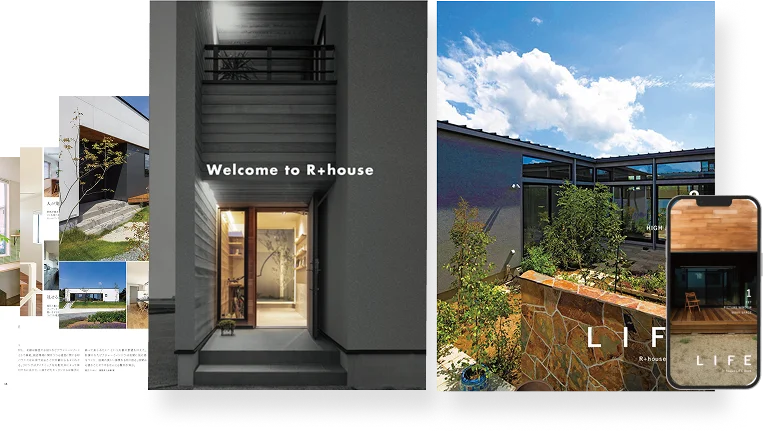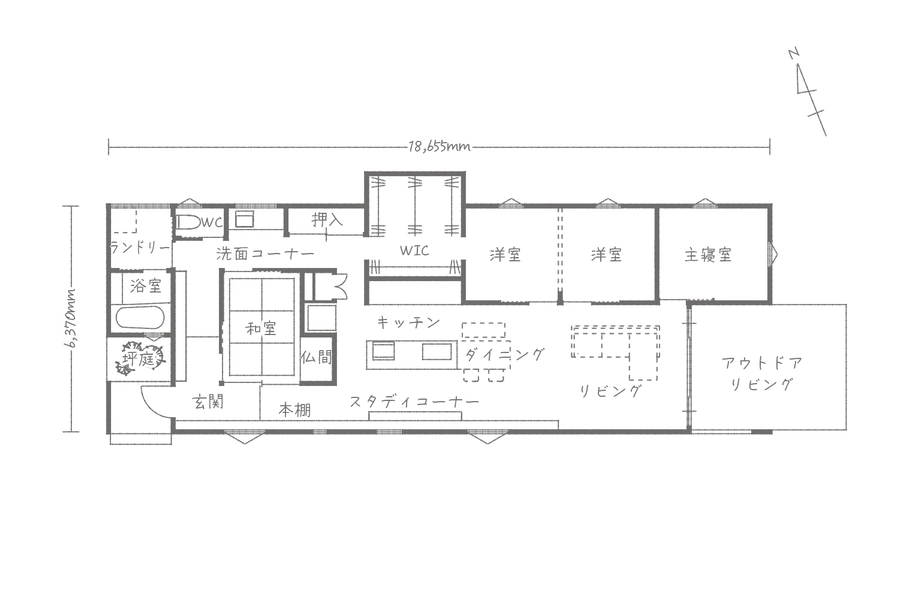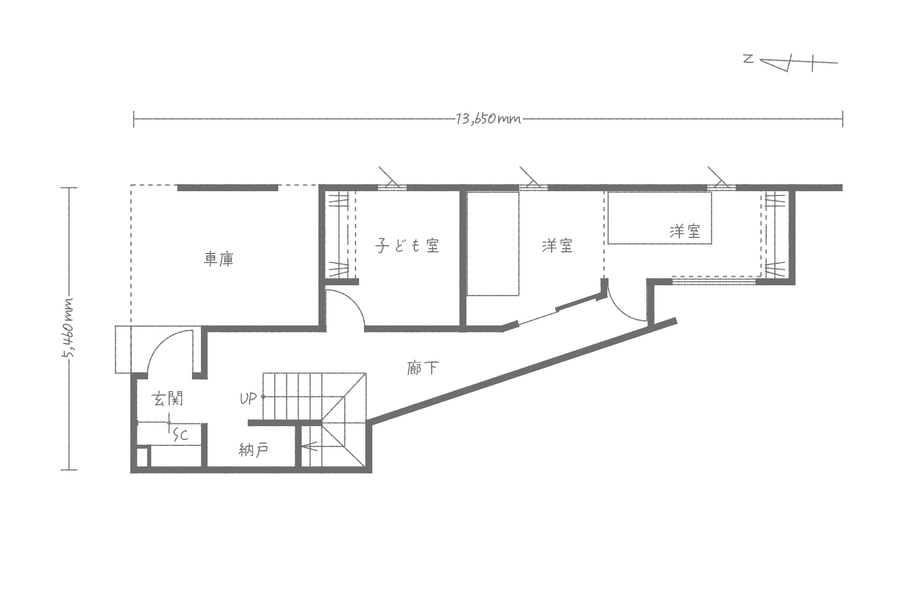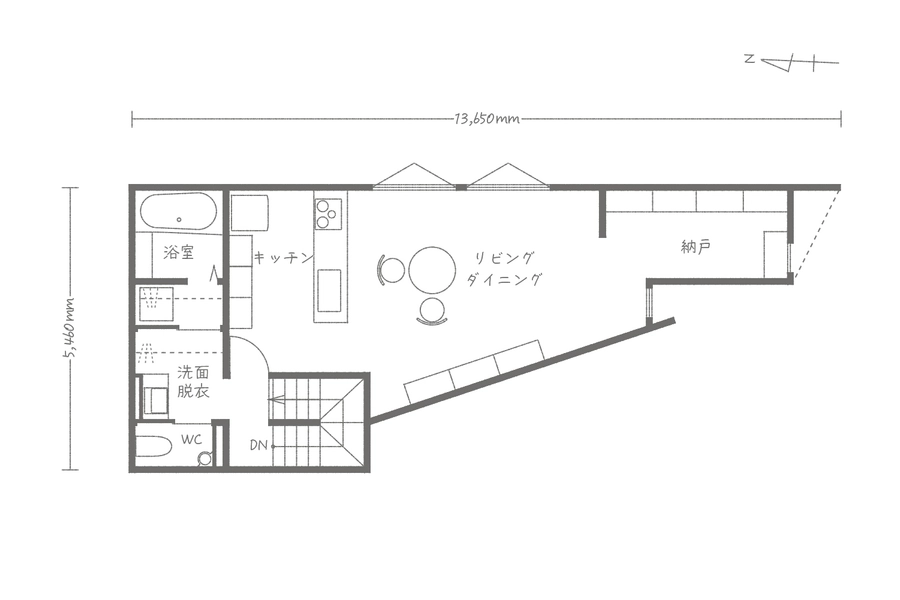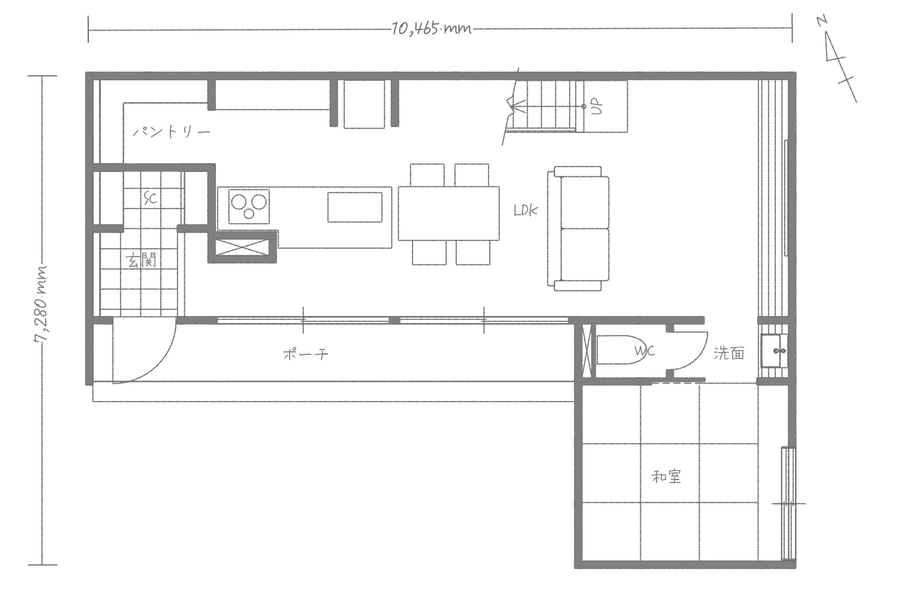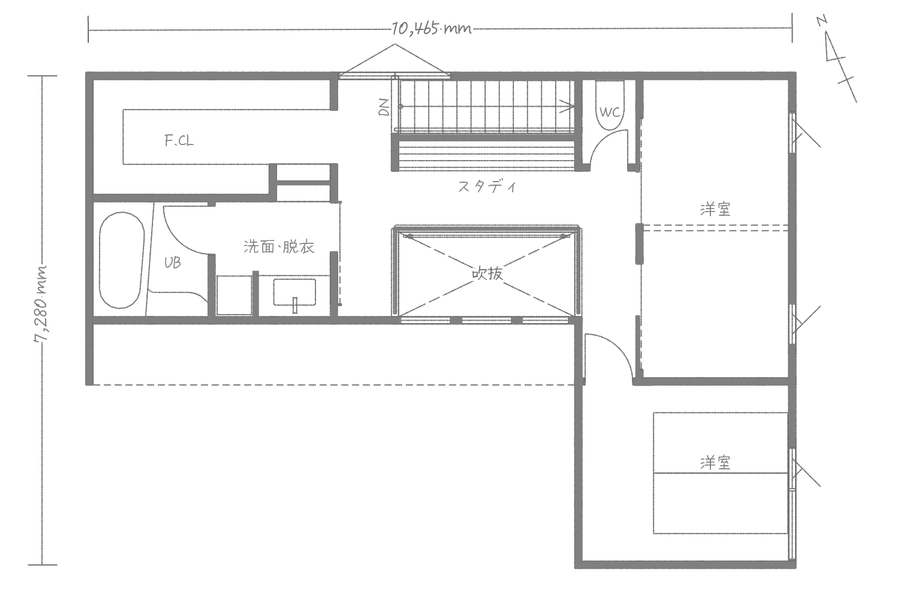R+houseの注文住宅の施工事例
全国300件以上のR+houseネットワークの注文住宅の施工事例をご紹介します。建築家がお客様の想いに寄り添って設計した施工事例をご覧ください。
305件



自然に溶け込む平屋
長野県軽井沢町



豊かで美しい空間が曖昧に繋がる家
愛知県東海市



守られた箱の中で気ままに暮らす平屋
和歌山県有田郡



アウトドアリビングを囲む家
埼玉県入間市



田園の暮らしを愉しむ土間リビングの平屋
千葉県船橋市



閑静な住宅地に建つ ゆとりの平屋
熊本県荒尾市



海を切り取る平屋
島根県益田市



広がり溢れる 外観が心地よい平屋
愛知県蒲郡市



角地に建つモニュメントのような家
愛知県日進市