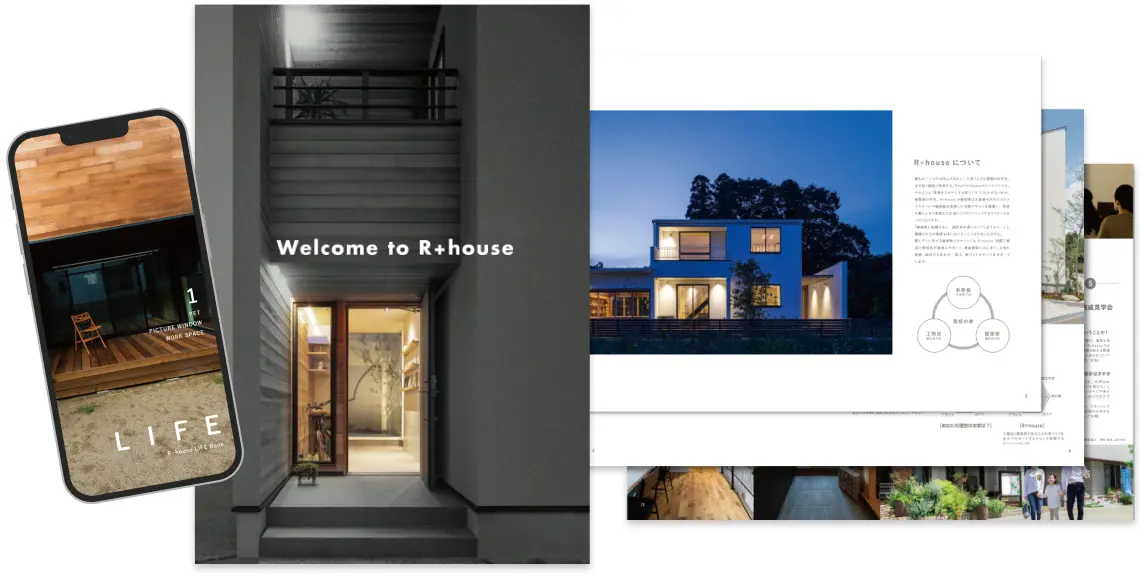地鎮祭とは?
 写真②地鎮祭の仮設テント.jpg 89.93 KB地鎮祭とは、「じちんさい」のほか、「とこしづめのまつり」と読むことがあり、工事の無事を祈ることを目的に行う儀式のことです。
写真②地鎮祭の仮設テント.jpg 89.93 KB地鎮祭とは、「じちんさい」のほか、「とこしづめのまつり」と読むことがあり、工事の無事を祈ることを目的に行う儀式のことです。また、地鎮祭は、その土地を守る神を祭る意味も持ちます。
日本では昔から地主神を大切にする文化が根付いており、その土地に眠る神様から土地を使用する許可を得ることで、長く住める丈夫な建物となり暮らす人々が幸せな生活を送れるとされています。
地鎮祭の歴史
地鎮祭は今から1200年以上も前に始まったとされ、古い歴史を持つ儀式です。日本最古の歴史書とされる「日本書紀」にも記されており、持統天皇の時代に藤原京の造営のために「鎮め祭らしむ儀式」が催されたとされています。さらに、さかのぼると弥生時代に存在した高床式住居の土の中から勾玉という鎮物(しずめもの)が発見された例もあります。
ただ、地鎮祭が広く普及したのは、建築技術が向上した江戸時代後半になってからであり、家に対する関心が高まったためとされているのです。
上棟式とは違うの?
 写真③幣束.jpg 92.77 KB
写真③幣束.jpg 92.77 KB地鎮祭のほかに上棟式(じょうとうしき)という儀式もあります。
住宅の工事を始める前に行われる地鎮祭に対して、上棟式は住宅の骨組みから屋根までといった基本構造が完成した際にお祝いする儀式です。屋根の最も高い位置の部材「棟木(むなぎ)」が配されたことを祝う目的を持ちます。
上棟式は現場で大工職人をまとめる棟梁が仕切る儀式であり、お施主様が建築関係者などに料理やお酒を振舞います。最近では見かけることが少なくなった餅投げも上棟式で行う儀式の一つです。
竣工式
竣工式(しゅんこうしき)は、住宅の完成を祝い感謝する儀式です。神事、そして完成した住宅のお披露目の2つの要素が含まれるイベントといえます。竣工式には、神事のみの場合、祝賀会を行うケース、その両方を合体させたものもあります。
地鎮祭をするには?
 写真④地鎮祭で祭壇に向かい建築工事の安全祈願を祈祷する神主.jpg 96.79 KB地鎮祭を実施する際は、神主さんへ依頼するのがほとんどです。
写真④地鎮祭で祭壇に向かい建築工事の安全祈願を祈祷する神主.jpg 96.79 KB地鎮祭を実施する際は、神主さんへ依頼するのがほとんどです。ただし、宗教によってはお坊さんや神父さんなどに依頼するケースもあります。古い歴史のある地鎮祭ですが、最近では地鎮祭を実施する家庭が減っている傾向にあり、何をするのか分からない場合も多いでしょう。
そのため、建築を考えるエリアに長く住んでいる方や、地域密着型の建築会社・工務店などに相談してみるのもおすすめです。建築会社や工務店であれば、工期に合わせて日程調整をしてくれます。
R+houseでの家づくりは、高性能で快適な住まいの提供を心がけています。さらに、勉強会や無料相談なども実施しているため、家づくりのことだけでなく、住宅に関する行事、着工、アフターサポートにいたるまで、気になることは何でもご相談ください。
地鎮祭の費用相場は?
地鎮祭で用意するもの
 写真⑤地鎮祭の祭壇.jpg 94.3 KB
写真⑤地鎮祭の祭壇.jpg 94.3 KB地鎮祭を行う際には、神主さんを招く費用をはじめ、お供え物など準備することが多くあります。ここでは、地鎮祭で準備するもの紹介します。
玉串料(初穂料)
地鎮祭では、儀式を執り行う神主さんへのお礼として、玉串料(初穂料)を準備する必要があります。現金を祝儀用ののし袋に包み、神主さんへお施主様から直接お渡しするケースがほとんどです。
玉串料の相場は2~5万円ほどとされていますが、神社によっては金額が決まっている場合もあるため、予約の際に確認しておくといいでしょう。のし袋は中袋がある蝶結びの紅白のものを用意します。筆ペンや毛筆を使用し、「御玉串料」または「御初穂料」などと表書きします。
お供え物
地鎮祭の依頼先にもよりますが、基本的にお供え物の準備はお施主様が行います。地鎮祭でお供えするものは、奉献酒や米、海の幸、山の幸、野菜、果物、塩などさまざま。そのほかにも神社から指定があれば準備します。さらに、その地域ならではのもので準備する場合もあるため、事前に調べておくと安心です。
なお、支柱として使用する竹や、祭壇の周りに張り巡らすしめ縄などは、お施主様ではなく神社のほか、建築会社や工務店が基本的に用意します。以下では、実際に準備するお供え物の例をあげていきます。
・米と塩は1合程度を準備
・水は200~500ml程度を準備
・酒はのし付きで、一升瓶1本または2本箱が主流
・海の幸は、鯛(なければスルメ)、昆布、海苔など
・野の幸は、大根、にんじん、なす、トマトなど
・山の幸は、バナナ、りんご、みかん、いちごなど
盃
地鎮祭では、御神酒を最後に飲むために使用する盃(さかずき)を準備します。参加した全員に御神酒を配るので、盃は人数分用意することが基本です。盃の種類には、「高杯」や「かわらけ」などがあります。
「高杯」は、おちょこよりも若干大きいサイズで、底が高くつくられている器。「かわらけ」は、釉薬(うわぐすり)をかけていない素焼きの陶器です。
盃がない場合は、升や湯呑を使う場合があるほか、紙コップなどで代用しても問題ありません。升は記念品として、名前や年月日を入れたものをインターネットなどで購入するご家庭もあります。
榊
榊(さかき)は、祭壇や常緑の神棚に供える植物です。年中青々とした葉をつける榊は、縁起がよいとされ地鎮祭などの神事でよく使用されています。榊は花屋などで購入できるため、5本ほど準備しておきましょう。なお、用意できない場合は、杉や楠といった他の常緑樹で代用します。
半紙
お供え物を盛るための三方の下に敷く半紙を準備します。地鎮祭で使う半紙は、一帖(20枚ほど)用意しておくのが一般的です。半紙は、事務用品店で購入できるほか、100円ショップやスーパーマーケットなどの文具コーナーにも置いてあるため、手軽に購入できます。
挨拶まわりの粗品
振動や騒音が発生する可能性のある工事に備えて、地鎮祭後には近隣への挨拶まわりを行います。その際、お菓子やタオルといった粗品を準備するのが一般的です。受け取る相手が気をつかわずに済む品がよく、金額も500~1,000円ほどにおさめるのが無難といえます。
地鎮祭の流れ
 写真⑥鍬入れ.jpg 90.97 KB
写真⑥鍬入れ.jpg 90.97 KB地鎮祭に要する時間は、80~100分ほどとされています。ここからは、一般的な地鎮祭の流れを見ていきましょう。
開式の辞
お施主様とそれ以外の参列者が祭壇にむかって右側、建設会社や工務店、工事関係者などが左側に並びます。参列する方全員が揃った時点で、進行者が儀式の開始を宣言します。
修祓の儀(しゅばつのぎ)
開式のあと、まず、祭壇と土地、参列する方をお浄めします。進行役の方の指示に従い全員で起立、神職がお祓いをする間は頭を少し下げておきます。再度、進行役のアナウンスで着席。
降神の儀
降神の儀(こうしんのぎ)は、住宅を建てる土地の神・地域の氏神を迎えるための儀式です。神職が声を発し神様の降臨を告げます。修祓の儀同様に、進行役の方の指示により起立後、神様をお迎えしている間は頭を下げ、再度アナウンスで着席します。
献饌
献饌(けんせん)は、祭壇にお供えした山の幸や海の幸などを神様に差し上げるための儀式です。献饌は、着席したまま待ちます。
祝詞奏上
祝詞奏上(のりとそうじょう)は、神職が祝詞(のりと)を読み上げます。この土地に家を建てることを告げて、工事の安全を祈ることが目的です。祝詞奏上も進行役の方のアナウンスに従い、起立・着席となります。
切麻散米
切麻散米(きりぬささんまい)は、神職が住宅を建てる土地の四隅に神酒と米、塩をまいて清める儀式です。四方祓(しほうはらい)とも呼ばれています。切麻散米の間は、座ったまま静かに待ちます。
地鎮の儀
地鎮の儀(じちんのぎ)は、その土地の神に着工を告げる儀式です。地鎮祭の工程のなかでも重要な部分といえます。地鎮の儀は、誰かが一人で行うのではなく、お施主様を含め工事を行う施工会社や関係者も一緒に行います。
きれいな円錐形の山を砂でつくり、そこへ草を立てます。設計者が鎌を持ち「刈初(かりぞめ)」、お施主様が鋤(くわ)を持ち「穿初(うがちぞめ)」、施工会社の担当者が鍬(すき)を持ち「土均(つちならし)」の真似事を行うのです。その後、神職が鎮め物をおさめます。
玉串奉奠
玉串奉奠(たまぐしほうてん)は、玉串を神前に供えて土地の神様への崇敬をあらわす儀式です。玉串とは、榊に「紙垂(しで)」をつけたものになります。この玉串奉奠は、お施主様だけでなく参列する方全員で行います。
撤饌の儀
撤饌の儀(てっせんのぎ)は、神前に供えたお供え物を神職が下げる儀式です。撤饌の儀は、座ったまま静かにその工程を見守ります。
昇神の儀
昇神の儀(しょうじんのぎ)は、迎えた土地の神様が変えるための儀式であり、参列する全員が起立をして拝礼します。
閉式の辞
閉式の辞(へいしきのじ)は、地鎮祭の終了を告げる挨拶です。神主が終了を告げると、地鎮祭が滞りなく終了したことになります。
神酒拝戴
神酒拝戴(しんしゅはいたい)は、神前に供えられたお神酒をいただくことで、直会(なおらい)の儀ともいいます。ここまでが、地鎮祭の流れであり、地鎮祭後に近所への挨拶まわりをするのが一般的です。住宅の工事は騒音などで迷惑をかける場合があるので、近所への挨拶まわりは必須といえます。
近所への挨拶は、自身の家の両隣、向かい3軒、裏3軒までするのがマナーとされています。
地鎮祭に関するよくある疑問
 写真⑦悩む若い夫婦のイラスト.jpg 61.3 KB
写真⑦悩む若い夫婦のイラスト.jpg 61.3 KBここからは、地鎮際に関するよくある疑問について解説していきます。
疑問1:地鎮祭は行わなくても問題はない?
地鎮祭は、長い歴史を持つ日本の伝統行事ではありますが、住宅を建てる際に必ず行わなければならないわけではありません。実際に、最近では予算やスケジュールなどの都合上、地鎮祭を行わないケースも増えています。
義務的なものではないため、依頼する建築会社との相談で、やるかやらないかをお施主様が決められます。ただ、地鎮祭の目的は、住宅を建てる土地への敬意を示すことです。そして、新しい生活をスタートさせるための節目となります。また、お施主様をはじめ、住宅の建築に携わる方が一同に会する貴重な場ともいえます。こういった事情や価値観などを考慮したうえで、地鎮祭を実施するのか検討することが大切です。
疑問2:地鎮祭を行うのに適した日はある?
地鎮祭は、基本的にお施主様の都合のいい日で行うケースが多いです。しかし、「大安」「友引」「先勝」など、吉日といわれる日の午前中を選ぶとよいとされています。吉日を気にされる方は、前もって先の予定を確認しておくといいでしょう。
疑問3:地鎮祭の服装やマナーは?
地鎮祭の際の服装に決まりはありません。しかし、神事のため、フォーマルな服装が一般的とされています。土地の神様への礼節の心を持ち、清潔感のある整った服装がおすすめです。
万が一、服装に迷うようなことがあれば、スーツタイプのジャケット、ネクタイを準備しておくと安心です。礼服まで用意する必要はありませんが、身だしなみには気をつけましょう。
神事である地鎮祭では、その土地の神様や関係者への礼儀を重んじることが重要視されます。そのため、神主さんや施工を請け負う担当者たちへの挨拶はしっかり行いましょう。さらに、今後お付き合いが始まる近隣の方々への挨拶まわりも、マナーとして忘れてはいけません。
疑問4:地鎮祭は雨天の場合も行う?
地鎮祭は、雨天の場合でも予定通り行われるケースがほとんどです。「雨降って地固まる」という慣用句があるように、困難や悪いことがあった後に、物事が落ち着いてよい方向に進むという意味合いがあり、雨が降ることは縁起がよいとされています。
雨は神様からの祝福と捉えることができるため、雨が降っても延期せずに開催される可能性が高いでしょう。しかし、豪雨や台風などの悪天候で安全の確保ができない場合は、日程を改める場合もあるので、依頼する建設会社や工務店に相談しておくと安心です。
安心安全に暮らせる注文住宅ならR+houseネットワークの工務店にお任せ!
 写真⑧神奈川県_白い外壁の家の裏側.jpg 256.53 KB
写真⑧神奈川県_白い外壁の家の裏側.jpg 256.53 KB地鎮祭の概要や流れについて紹介しました。工事の安全や住宅完成の無事を祈って行われる地鎮祭。スムーズに執り行うためにも事前に調べ、住宅会社などに相談しながら準備していくことが大切です。地鎮祭を行い、安心安全な家づくりを進めていきましょう。
R+houseネットワークの工務店では、家づくりに関する相談を無料で受け付けております。土地探しをはじめ、資金計画、家づくりの流れや特徴など、気になることは全てご相談ください。また、住宅関連のさまざまなイベントも開催しているため、お近くの会場までお気軽にお越しください。
>>家づくりのプロである建築家と建てる注文住宅「R+house」についてはこちら