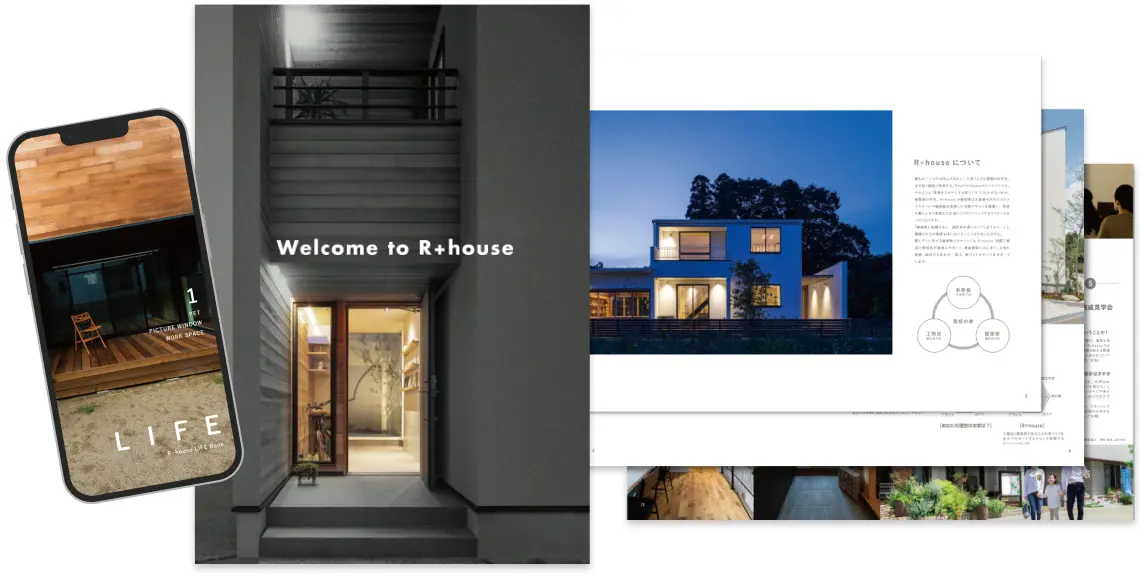天井の高さはどうやって決める?
 写真②織り上げ天井.jpg 82.27 KB家の快適性を左右するポイントのひとつに、天井の高さがあります。
写真②織り上げ天井.jpg 82.27 KB家の快適性を左右するポイントのひとつに、天井の高さがあります。実は私たちが普段過ごす部屋の天井の高さには、法律(建築基準法)でルールが定められています。建築基準法では、居室における天井の高さは2.1m以上と定められており、多くの一般的な住宅では、2.4mに設定されていることが多いです。天井が高いと、部屋全体が広々と感じられ圧迫感が少なく開放的な空間で暮らせるというメリットがありますが、家を建てる際には法律を守る必要があるため、好きなだけ天井を高くできるわけではありません。廊下やトイレなどを除いた居室部分の高さは、基準を満たすように設計する必要があります。
ここで一つ覚えておきたいポイントがあります。それは、建築基準法で定められている天井高とは「最低の高さ」ではなく「平均の高さ」であるという点です。各部屋の天井高の平均は、以下の簡単な計算で求められます。
「部屋の容積÷床面積=天井高の平均」この計算式で求められた平均の高さが2.1メートル以上であれば良いため、一部分が2.1メートルより低い場所があったとしても、部屋全体の平均として基準をクリアしていれば問題ありません。
参考元:国土交通省|建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)
R+houseネットワークの工務店が建てる住宅の天井高は?
R+houseネットワークの工務店では、基本的に天井高が2.4mに設定されています。この高さに設定しているのは以下の理由があります。
コストダウンのため
日本で木造住宅を建てる場合、モジュールという共通の寸法を使用しています。例えば、壁や天井など内装の下地材として使用する石膏ボードは縦の長さが2.4mになるようにカットされています。そこで、天井高を同じく2.4mに設定しておけば、資材をカットせずにそのまま使用可能です。しかし、天井高を2.2mにする場合は、20cmカットしなければいけません。資材をカットする加工代がかかるうえ、材料に無駄が生じてしまうでしょう。
そこで、R+houseネットワークの工務店では材料を無駄にしないために、効率良くすべて使いきれる2.4mの天井高を標準としているのです。>>参考コラム:注文住宅の建築相場はいくら?コストダウンのOK・NGポイントもご紹介
工期を長引かせないため
R+houseネットワークの工務店では、さまざまな独自の建築ルールを定め、工期を短縮できるように工夫を凝らしています。天井高に合わせて材料をカットしたり繋いだりするなど、現場での加工が増えると時間がかかり、工期の長期化に繋がりかねません。現場で加工する作業は、一つひとつは短時間でできるものでも、ちりも積もれば山となるように、工期が伸びてコストがかさむ要因になると言えるでしょう。
このような無駄な材料・時間が極力生じないよう、R+houseネットワークの工務店では設計段階から工夫を凝らしています。
天井を高くするメリット
 写真③メリットとデメリットの説明をする若い女性.jpg 72.78 KB
写真③メリットとデメリットの説明をする若い女性.jpg 72.78 KBコストをかけても、天井を高くしたいという方もいるでしょう。R+houseでは吹抜けをつくることで天井を高くした事例も少なくありません。ここからは、天井を高くするメリットを解説します。
開放感がアップする
天井の高さを高くするメリットは、なんといっても開放感です。天井までの距離があり、空間に広がりが生まれるので、同じ面積の部屋であってもより広く感じるでしょう。反対に、どれだけ広い部屋でも天井が低いと圧迫感を感じる要因に。広々した空間でリラックスしたいなら、天井の高さにこだわると良いでしょう。
採光面で有利
部屋の天井を高くすると、その分壁面も増えます。そのため、より広い窓を確保できて光を多く室内に取り入れられるでしょう。また、窓の数を増やしたり、より高い位置に設置したりといった選択肢も増えます。明るい空間を確保したいなら、天井は高いほうが好ましいといえます。
換気しやすい
高窓を設置して効率よく換気できる点も、天井を高くするメリットです。とくに、高窓は室内で温められた空気を屋外に排出してくれるため、スムーズに換気できるでしょう。また、窓の数を増やすと家全体の通気性が良くなり、効率よく換気できます。
ひと部屋当たりの収納量がアップする
天井の高さを確保すると、部屋の空間にも余裕が生まれます。ロフトを設置して収納にしたり趣味を楽しむ場所になったりと、空間の使い道が広がります。また、壁面収納を作る場合は、天井が高ければ高いほど収納量もアップします。
インテリアの選択肢が広がる
背の高い観葉植物や大きな家具も選択肢に入り、インテリアの幅が広がります。さらに、壁面が増えるため大きなアートを飾るスペースも確保可能です。吊り下げるタイプの照明も設置でき、おしゃれな部屋を演出できるでしょう。
R+houseネットワークの工務店では、お施主様が理想とする家を建築家がデザインします。ライフプランを考慮して、デザイン性が高くて暮らしやすい家をご予算内でご提案します。理想の暮らしを叶えるオシャレな家を建てたい方は、お近くのR+houseネットワークの工務店までお問い合わせください。
天井を高くすることのデメリット
天井を高くすると開放感が得られて明るい家になりますが、デメリットもあるので覚えておきましょう。
設計や建築コストがかさむ
冷暖房効率が悪くなる
照明の交換や掃除が大変
照明が切れてしまった場合、天井が高い家では交換が大変になることも。交換頻度が少なくて済むLED電球の採用をするのがおすすめです。
また、表しの梁がある場合は、梁に溜まったほこりを掃除するのも一苦労です。自分で交換や掃除をする場合は、柄が長い掃除道具で対処できないこともないですが、掃除には労力や時間がかかるうえ高い位置からの転落リスクもあります。業者に依頼することを検討すると良いでしょう。
特注のカーテンが必要な場合がある
天井が高すぎると、一般的に販売されているカーテンでは長さが足りない可能性があります。したがってオーダーメイドでカーテンを作る必要があり、コストと時間がかかる可能性があることを念頭に置いておきましょう。なお、コの字型の間取りを採用するなどの工夫で、カーテンを極力使わない家にすることも可能です。
部屋によって理想の天井高は異なる
すべての部屋で天井が高い家を作ればいいかというと、そうではありません。部屋の用途によってベストな天井高は異なります。ここでは、天井が低い方が過ごしやすい部屋と高い方が過ごしやすい部屋を開設します。
天井が低い方が快適に過ごせる部屋
低い天井の採用をおすすめする部屋は、以下の通りです。
・和室
・寝室
・トイレ
・書斎 など
座って過ごす時間が長い場所は、天井を低くすると落ち着いて過ごせます。天井が高すぎると、座ったときに天井までの距離を感じて落ち着かなくなる可能性があるでしょう。また、書斎やトイレなどの狭いスペースで天井を高くし過ぎるのは、壁が迫っているように感じてかえって圧迫感を与える要因に。座って過ごす部屋や狭い空間の天井高は、2.2~2.4m程度にするのがおすすめです。
天井が高い方が快適に過ごせる部屋
天井を高くすると快適に過ごせるのは、以下の部屋です。
・リビング
・ダイニング
・子ども部屋 など
家族が集まる空間は、天井を高くすることで開放感が出ます。家族やゲストが大人数集まっても圧迫感を感じないように、高い天井高を確保するのが良いでしょう。また、子ども部屋では2段ベッドやロフトベッドなどを設置する可能性があるため、天井を高めにしておくと圧迫感を減らせます。天井を高めにする部屋では、2.4m以上の高さを確保するのがおすすめです。
>>参考コラム:子ども部屋のインテリアをおしゃれに!おすすめ施工事例を10選ご紹介
開放的に感じられる天井のアイデア3選
開放感を演出するアイデアには、以下のものが挙げられます。
・吹き抜け
・勾配(こうばい)天井
・ハイドア
ひとつずつ詳しく解説します。
吹き抜け
吹き抜けとは、上下の階が縦の空間で繋がっているスペースのことを指します。1階、2階ともに天井高は標準のままでも、上下の空間をひと続きにすることで視界を遮るものがなくなり、開放感が得られるでしょう。さらに、吹き抜けを採用すると高い位置に窓を設置でき、明るさも確保できます。
吹き抜けの施工事例①|5世帯9人が暮らす白い大きな家
 写真④大きな窓と吹き抜けのある土間リビング.jpg 48.25 KB9人の大家族が暮らす大きな家。土間リビングの上部に吹き抜けを作りました。
写真④大きな窓と吹き抜けのある土間リビング.jpg 48.25 KB9人の大家族が暮らす大きな家。土間リビングの上部に吹き抜けを作りました。掃き出し窓と吹き抜けの上部の窓からは、光がたっぷり室内に差し込みます。
場所:奈良県 北葛城郡
階数:2階建て
延床面積:208.53㎡(63.08坪)
敷地面積:243.83㎡(73.75坪)
>>施工事例:奈良県北葛城郡「家族との距離が近すぎず離れすぎない 心地の良い家」
吹き抜けの施工事例②|吹き抜けにうんていを設置した家
 写真⑤うんていが設置された吹き抜けと土間.jpg 44.71 KB庭に繋がる土間の上部に吹き抜けを設けました。
写真⑤うんていが設置された吹き抜けと土間.jpg 44.71 KB庭に繋がる土間の上部に吹き抜けを設けました。背が高い観葉植物を配置して、目を引くインテリアに。LDKからもグリーンを楽しめます。また、吹き抜けの高さを活かしてうんていを設置しました。軽い運動をしたり、植物をつるしたりとバリエーション豊かな使い道があります。
場所:和歌山県 和歌山市
階数:2階建て
延床面積:99.36㎡(30.05坪)
敷地面積:142.77㎡(43.18坪)
>>施工事例:和歌山県和歌山市「心が温かくなる居心地の良い家」
吹き抜けの施工事例③|インテリアが光るこだわりの家
勾配天井
屋根の形状に合わせた天井のことを「勾配天井」といいます。通常、天井と屋根との間には天井裏もしくは屋根裏とよばれるデッドスペースができます。勾配天井を採用すると、デッドスペースを無駄なく利用できるだけでなく、明るく開放感のある部屋が実現可能に。屋根の高さギリギリまで室内にできるでしょう。
勾配天井の施工事例①|落ち着く大人空間を叶えた家
 写真⑦勾配天井で開放感のあるLDK.jpg 38.34 KBリビングに勾配天井を採用。高い部分では4mの天井高を確保して、室内に開放感を演出しています。
写真⑦勾配天井で開放感のあるLDK.jpg 38.34 KBリビングに勾配天井を採用。高い部分では4mの天井高を確保して、室内に開放感を演出しています。片側の壁には壁面収納を造作して、ピクチャーウインドウから外の景色を楽しめるように工夫を凝らしました。
場所:和歌山県 有田郡
階数:平屋
延床面積:108.06㎡(32.68坪)
敷地面積:466.71㎡(141.17坪)
>>施工事例:和歌山県有田郡「守られた箱の中で気ままに暮らす平屋」
勾配天井の施工事例②|縦に広がる温かみのある空間
 写真⑧木材を使用した勾配天井で温かみのあるリビング.jpg 56.21 KB和風テイストの長屋で、LDKに勾配天井を取り入れました。
写真⑧木材を使用した勾配天井で温かみのあるリビング.jpg 56.21 KB和風テイストの長屋で、LDKに勾配天井を取り入れました。天井には木材を使用して、温かみのある空間に。左右で天井の高さを変えて、空間を隅々まで活かした家が完成しました。
場所:愛知県 北名古屋市
階数:平屋
延床面積:91.85㎡(27.78坪)
敷地面積:215.41㎡(65.16坪)
>>施工事例:愛知県北名古屋市「modern長屋」
勾配天井の施工事例③|シックで落ち着いた空間の家
 写真⑨シックでホテルライクな雰囲気の勾配天井のリビング.jpg 41.94 KB角度のついた勾配天井を取り入れて、広々とした空間を作りました。
写真⑨シックでホテルライクな雰囲気の勾配天井のリビング.jpg 41.94 KB角度のついた勾配天井を取り入れて、広々とした空間を作りました。中庭から取り入れた光が室内に差し込み、明るさと落ち着く空間を演出。ホテルライクな暮らしができる家になりました。
場所:岐阜県 岐阜市
階数:平屋
延床面積:91.5㎡(27.67坪)
敷地面積:230.2㎡(69.63坪)
>>施工事例:岐阜県岐阜市「大きな間のある平屋」
ハイドア
一般的なドアの高さは約2mで、設置するためにはドアの上端から天井までの間に垂れ壁を作らなければいけません。しかし、天井まで高さのあるハイドアを採用すると、垂れ壁を作らずに床から天井までを1つの面にできます。視界を遮る垂れ壁を作らなくて良くなり、ドアを開けたときに空間がより広くスッキリとした印象をもたらします。また、高さがある家具家電の搬入もしやすくなるでしょう。
ハイドアの施工事例|ドアもリビングのデザインの一部にした家
 写真⑩ハイドアの設置されたリビング.jpg 40.63 KBリビングにハイドアを設置した家です。
写真⑩ハイドアの設置されたリビング.jpg 40.63 KBリビングにハイドアを設置した家です。垂れ壁がなく、ドアをおしゃれに配置できます。デザイン性と利便性を叶えた家が完成しました。
場所:東京都 昭島市
階数:2階建て
延床面積:88.6㎡(26.8坪)
敷地面積:143.86㎡(43.51坪)
>>施工事例:東京都昭島市「ゲートが迎える家」
天井の高さに迷ったらR+houseネットワークの工務店へ
天井の高さは、部屋の用途や面積によってベストが異なります。今回ご紹介したポイントを参考に、快適に過ごせる高さを検討してください。
R+houseネットワークの工務店では天井高を2.4mに設定して、材料を無駄なく使っています。また、現場の作業時間を短縮して、短い工期で家の完成を目指します。お施主様の負担を軽くするコストカットにも余念がありません。建築家との3回の打ち合わせで、理想の家のデザインをご提案します。マイホームをお考えの方は、是非一度お近くのR+houseネットワークの工務店へ足を運んでみてください。
>>天井の高さなどにもこだわったマイホームが建てられる!R+houseのデザインについてはこちら