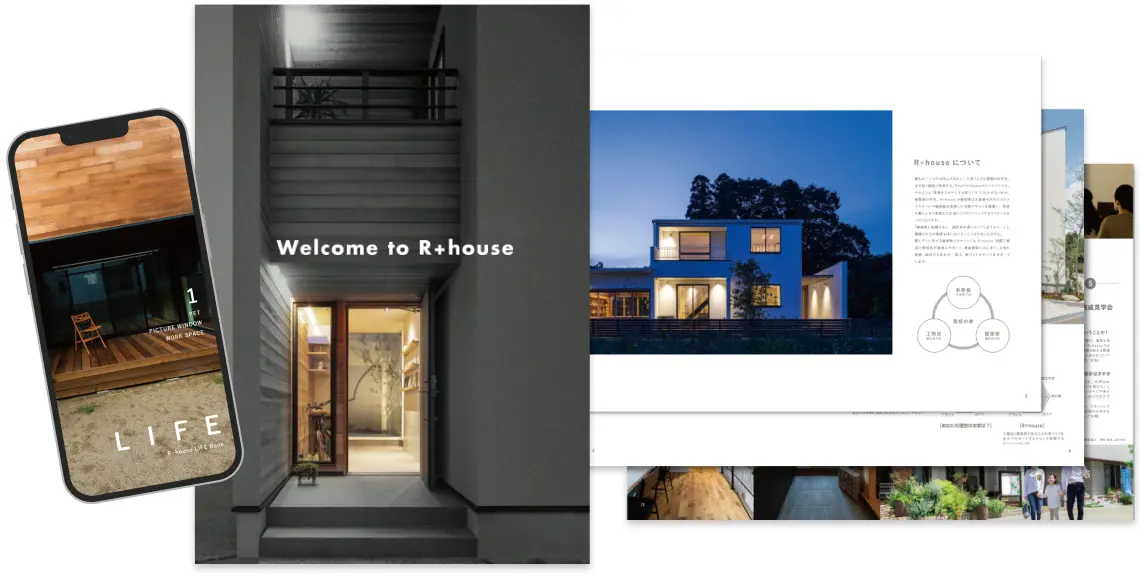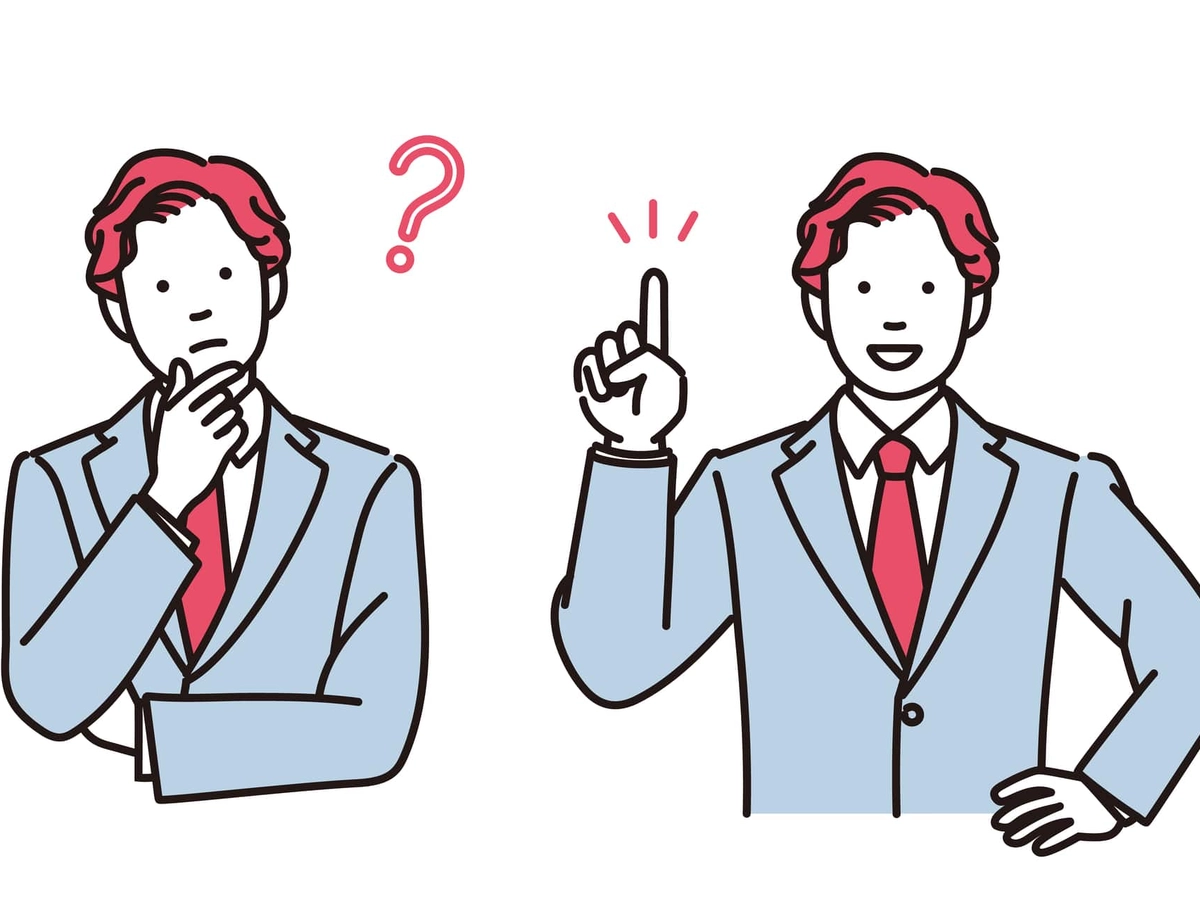固定資産税は平屋と2階建てでどう違う?
 写真②AとBを比較をして考える男性-min.jpg 70.64 KB
写真②AとBを比較をして考える男性-min.jpg 70.64 KB固定資産税は、平屋か2階建てかを決める際の判断材料にもなる重要なポイントです。まずは、固定資産税の概要と、平屋および2階建てにおける違いを解説します。
そもそも固定資産税とは?
固定資産税は、毎年1月1日時点において、土地・家屋・事業用の機械など「固定資産」を所有している人が、市町村に納める地方税です。ただし、東京都23区では、都に対して納税します。固定資産の具体例を以下にまとめました。
| 固定資産の区分 |
具体例 |
| 土地 |
田畑・住宅地・塩田・鉱泉地・山林・牧場・池沼・原野など |
| 家屋 |
住宅・店舗・工場・倉庫など |
| 償却資産 |
事業者所有の構築物・飛行機・船舶・車両・運搬具・備品など |
固定資産税は、市町村の教育や福祉、道路整備といった住民サービスに使われる重要な財源となっています。
参考元:総務省|固定資産税
固定資産税の仕組み
住まいにおける固定資産税は、土地と建物それぞれに対して課税されます。国が定める「固定資産評価基準」に基づき、市町村が個別に評価額を決定し、それをもとに税額が決まるのが特徴です。ここで、土地と家屋における固定資産の評価方法をチェックしておきましょう。
| 固定資産の区分 |
評価方法 |
| 土地 |
・宅地の場合、主に道路(路線)に面する宅地の価格(路線価)を基に評価する「路線価方式」が用いられる。
・路線価が定められていない地域では、近隣の標準的な宅地の価格に比準して評価する。
・評価額は、国が公表する地価公示価格の7割程度が目安。 |
| 家屋 |
・評価対象の家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、それに経年劣化による減価(経年減点補正率)などを乗じて評価額を計算する。 |
家屋の評価額の算出に用いる「再建築価格」とは、評価時点において、対象とまったく同一の建物を同じ場所に新築した場合にかかる建築費用を指します。「再調達原価」と呼ばれることもあるでしょう。また、「経年減点補正率」は、住宅建築後の経過年数に応じて定められています。
土地および家屋の評価は、原則として3年に1回の頻度で見直されます。直近では2024年に評価替えが行われました。なお、2025年および2026年は、地価の下落が予想されており、土地価格を据え置くことが適切でないと判断された場合、修正が行われることがあります。
参考元:総務省|固定資産税参考元:一般財団法人 資産評価システム研究センター|令和7年度 固定資産税のしおり
固定資産税を具体的に左右する内容とは?
住宅の評価は再建築価格に基づきます。そのため、建築コストが高額な家では、固定資産税も高い傾向があるでしょう。
具体的には、構造や建材、設備などによって固定資産税の金額が変わります。たとえば、一般的に木造のほうが鉄骨造の住宅よりも、評価額が下がりやすいでしょう。というのも、木造住宅は鉄骨造に比べ、経年減価が早いとされているためです。
また、同じ構造であっても、屋根や外壁に使われる資材、キッチンの広さやグレード、システムバスの大きさ、トイレの数といった設備面も固定資産を左右します。
固定資産税は平屋と2階建てでどう違う?
平屋は2階建てよりも固定資産税が高額になる傾向があるといわれています。平屋の固定資産税に大きく関わるのが、敷地面積と使用する建材の量です。一般的に、平屋は2階建てと同じ延床面積を確保しようとすると、より広い土地を要します。そのため、土地の固定資産税が高額になりやすいでしょう。
また、同じ延床面積で建てた場合、平屋のほうが2階建てに比べて建築面積※が大きくなります。(※建築面積とは、住宅を真上から見た面積。)建築面積が広い平屋では、建物の土台となる基礎や屋根の面積が大きくなり、家づくりに必要な建材も多くなります。その結果、再建築価格が高く評価され、平屋では固定資産税が高くなる傾向があるのです。
住まいにおける固定資産税の計算方法
 写真③住宅模型と電卓-min.jpg 47.55 KB固定資産税は、課税標準額×標準税率1.4%で求められます。
写真③住宅模型と電卓-min.jpg 47.55 KB固定資産税は、課税標準額×標準税率1.4%で求められます。具体的な計算手順をステップごとに見ていきましょう。
参考元:総務省|固定資産税
ステップ1|土地・建物の固定資産の評価額(課税標準額)を算出する
固定資産税は、固定資産税の計算の基になるのが「課税標準額」です。土地と建物の両方について「課税標準額」を調べる必要があります。これは、対象の住まいがある市町村が調査し、個々に決定する「固定資産税評価額」を基に算出されます。
【家屋の場合】
原則として、「固定資産税評価額」がそのまま「課税標準額」となります。新築家屋の評価額は、市町村の家屋調査を経て決定されるため、建てるまで正確な金額は分かりません。一般的に、実際の建築費の50~60%程度が目安といわれています。
【土地の場合】
評価額に後述の「住宅用地の特例」を適用し、軽減された後の額が「課税標準額」となります。
ステップ2|課税標準額に税率を掛ける
ステップ3|特例措置による減額を計算する
 写真④指示指示棒を持ち注意を促すビジネスウーマン.jpg 70.13 KB
写真④指示指示棒を持ち注意を促すビジネスウーマン.jpg 70.13 KB固定資産税には、税負担を軽減するための特例措置があります。代表的なものが、課税標準額を軽減する「住宅用地の特例」と、税額そのものを減額する「新築住宅の減額措置」です。
住宅地特例の概要
住宅をはじめとする居住できる建築物を建てる敷地「住宅用地」は、低負担軽減のために、面積に応じて特例措置が講じられます。具体的な軽減率を表にまとめました。
| 住宅用地の区分 |
軽減率 |
| 200㎡(約60.5坪)以下の小規模住宅用地 |
評価額×6分の1 |
| 200㎡(約60.5坪)を超える部分の一般住宅用地 |
評価額×3分の1 |
例えば300㎡(約90.7坪)の住宅用地の場合、土地の200㎡(約60.5坪)分は評価額×6分の1、残りの100㎡(約30.2坪)は評価額×3分の1で計算します。
新築住宅特例の概要
新築住宅特例は、2026年3月31日までに建てられた新築住宅に適用される減額措置です。適用されると、居住部分に関する床面積120㎡(約36.3坪)までの固定資産税額が2分の1になります。
2階建て以下の住まいで特例が適用される期間は、一般住宅か長期優良住宅かなど、住宅の種類によって異なります。
| 住宅の区分 |
期間 |
| 一般住宅 |
3年度分 |
| 長期優良住宅 |
5年度分 |
ただし、土砂災害特別警戒区域や浸水被害防止区域といった災害レッドゾーンの中で、市町村による適正な立地を促すための勧告に従わずに建てられた特定の住宅は、この減額措置の対象外となる場合があります。土地を選ぶ際は、ハザードマップを十分確認するようにしましょう。
参考元:国土交通省|新築住宅に係る固定資産税の減額措置>>参考コラム:平屋に向いている土地選びと敷地条件は?家族人数別の必要な土地面積も紹介
ステップ4|土地・建物の固定資産税額を合算する
土地と建物、それぞれの手順で算出した税額を合算することで、トータルの固定資産税を算出できます。
固定資産税をシミュレーション|平屋・2階建てで比較
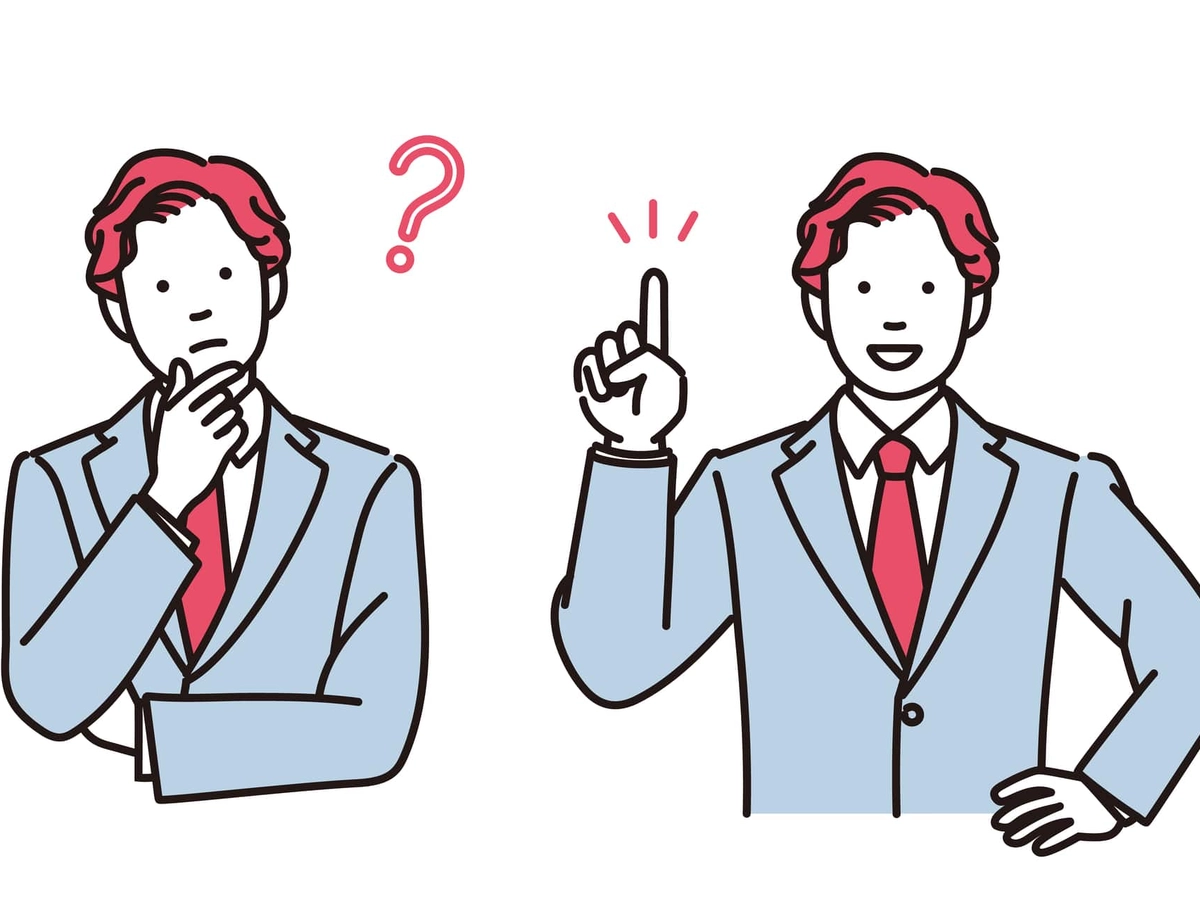 写真⑤考えている人と笑顔で解説するビジネスマンのシンプルイラスト-min.jpg 87.95 KB
写真⑤考えている人と笑顔で解説するビジネスマンのシンプルイラスト-min.jpg 87.95 KBここで、実際に平屋と2階建てで固定資産税がどのくらい異なるのか、シミュレーションしてみましょう。条件を以下のとおり設定し、それぞれの固定資産税を計算します。
・木造住宅を新築(一般住宅)
・延床面積30坪(約100㎡)
・建ぺい率50%・容積率80%の土地を購入
・土地価格は75万円/坪(約23万円/㎡)
・再建築価格は平屋で3,000万円、2階建てで2,600万円
・土地の評価額は購入価格の70%
・建物の評価額は再建築価格の60%
・固定資産税率は1.4%再建築価格は、基礎や外壁、屋根にかかるコストを考慮し、平屋のほうが高くなるように設定しました。
平屋の固定資産税をシミュレーション
まずは、平屋の固定資産税を計算してみましょう。
平屋|土地の固定資産税
建ぺい率50%の土地において、建築面積30坪(約100㎡)の平屋を建築する場合、少なくとも60.5坪(約200㎡)の広さが必要です。ここでは60.5坪の土地を購入したとします。
・土地の購入金額:75万円 × 60.5坪 = 約4,538万円
・土地の評価額:4,538万円 × 70% = 約3,177万円
・課税標準額:3,177万円 × 1/6(小規模住宅用地の特例) ≒ 約529.5万円
・土地の固定資産税額:529.5万円 × 1.4% = 約7.4万円
200㎡以下の土地については、評価額が6分の1に減額されることを踏まえ計算すると、平屋における土地の固定資産税額は、約7.4万円となりました。
平屋|建物の固定資産税
次に、平屋における建物の固定資産税を求めていきましょう。
・家屋の評価額(=課税標準額):3,000万円 × 60% = 1,800万円
・本来の税額:1,800万円 × 1.4% = 25.2万円
・家屋の固定資産税額:25.2万円 × 1/2(新築住宅の減額措置) = 約12.6万円
今回は建物の建築面積が約100㎡のため、建物全体に軽減措置が適用され、固定資産税額が2分の1になります。よって、建物の固定資産税額は約12.6万円となり、土地の固定資産税額を合算した金額は、約20.0万円でした。
2階建ての固定資産税をシミュレーション
続いて、2階建ての固定資産税をシミュレーションしましょう。
2階建て|土地の固定資産税
2階建ての住宅を建てる際は、平屋ほど広い土地面積を必要するケースは多くありません。建ぺい率50%かつ容積率80%の土地の場合、30坪(約100㎡)以上あれば2階建ての住宅を建てられるでしょう。30坪(約100㎡)の土地を購入した前提で、固定資産税額計算します。
・土地の購入金額:75万円 × 30坪 = 2,250万円
・土地の評価額:2,250万円 × 70% = 1,575万円
・課税標準額:1,575万円 × 1/6(小規模住宅用地の特例) ≒ 約262.5万円
・土地の固定資産税額:262.5万円 × 1.4% = 約3.7万円
土地の評価額が6分の1まで減額される特例を適用させた結果、2階建て住宅における土地の固定資産税額は約3.7万円となりました。
2階建て|建物の固定資産税
建築費をもとに、2階建て住宅における建物の固定資産税額を計算します。
・家屋の評価額(=課税標準額):2,600万円 × 60% = 1,560万円
・本来の税額:1,560万円 × 1.4% = 約21.8万円
・家屋の固定資産税額:21.8万円 × 1/2(新築住宅の減額措置) = 約10.9万円
税額が2分の1になる新築住宅の減額措置を適用し、建物の固定資産税を求めました。2階建ての土地と建物の固定資産税を合算した金額は、約14.6万円です。
平屋の延床面積が増えると税額はどのくらい変わる?
ここで、平屋の延床面積が広い場合の固定資産税もシミュレーションしてみましょう。再建築価格3,300万円・35坪の平屋を建てるとし、固定資産税を計算します。建ぺい率や坪単価などの条件設定は変わりません。
35坪の平屋|土地の固定資産税
35坪の平屋を建てるために必要な土地面積は70坪(約231㎡)とします。ここでは70坪の土地を購入したとします。
・土地の購入金額:75万円×70坪=5,250万円
・土地の評価額:5,250万円×70%=3,675万円
土地面積の231㎡分は評価額6分の1、残りの31㎡分は3分の1の減額対象です。評価額3,675万円を200㎡:31㎡の割合に換算すると、約3,182万円:493万円となります。
・200㎡部分の税額:(3,675万円 × 200/231 × 1/6)× 1.4% = 約7.4万円
・31㎡部分の税額:(3,675万円 × 31/231 × 1/3)× 1.4% = 約2.3万円
・土地の固定資産税額:7.4万円 + 2.3万円 = 約9.7万円
それぞれの税額を合算した約9.7万円が、35坪の平屋における土地の固定資産税額です。
35坪の平屋|建物の固定資産税
35坪の平屋の場合も、建物の固定資産税額を算出します。
・建物の評価額(=課税標準額):3,300万円 × 60% = 1,980万円
・本来の税額:1,980万円 × 1.4% = 約27.7万円
・家屋の固定資産税額:27.7万円 × 1/2(新築住宅の減額措置) = 約13.9万円
土地と建物の税額を合計した結果、35坪の平屋における固定資産税額は、約23.6万円となりました。
シミュレーション結果からわかること
延床面積30坪の平屋と2階建て、35坪の平屋、それぞれの固定資産税を、改めて表にまとめました。
| 住宅の種類 |
固定資産税額 |
| 30坪の平屋 |
約20.0万円 |
| 30坪の2階建て |
約14.6万円 |
| 35坪の平屋 |
約23.6万円 |
同じ延床面積の場合、2階建てよりも平屋の固定資産税が、約5.4万円高くなりました。また、平屋で比べた場合、延床面積が30坪から35坪に増えると、約3.6万円税額が増えることがわかります。
ただし、再建築価格は設備などにより大きく異なるため、今回のシミュレーションが常に当てはまるわけではありません。また、今回は新築住宅を条件としましたが、経年変化に伴い固定資産税額が変動することを念頭に置いてください。
平屋の固定資産税を抑える4つのポイント
 写真⑥黒板に書かれたポイントの文字と電球のイラスト-min.jpg 76.34 KB
写真⑥黒板に書かれたポイントの文字と電球のイラスト-min.jpg 76.34 KBここからは、平屋の固定資産税額を抑えるポイントについて見ていきましょう。
・間取りや設備をシンプルにする
・木造住宅を検討する
・長期優良住宅の平屋を建てる
・評価額を抑えられる土地を選ぶ
家づくりでは、間取りの工夫次第で延床面積を抑えられます。また、不要なオプションを付けずシンプルな設備を選べば、建物の評価額が高くなるのを防げるでしょう。また、鉄骨造よりも木造住宅のほうが、固定資産税額が低くなる傾向があります。
加えて、固定資産税の減額措置をより長く受けられる長期優良住宅の平屋を建てるのも有効な手段です。さらに、相場が低いエリアや変形地といった評価額が低い土地を選ぶのも良いでしょう。
R+houseネットワークの工務店は、木造の長期優良住宅の建築も対応可能です。工務店とR+houseネットワークの登録建築家が手を組むことで、変形地や狭いエリアでも、お施主様の理想を詰め込んだおしゃれな住まいを提案いたします。
>>参考コラム:木造建築は新築住宅に向いている?メリット・デメリットを徹底解説>>参考コラム:補助金が受けられる長期優良住宅とは?メリット・デメリットなど徹底解説
平屋と2階建てで迷ったらここをチェック
 写真⑦静岡県_すっきりとした白い外観 .jpg 389.57 KB
写真⑦静岡県_すっきりとした白い外観 .jpg 389.57 KB最後に、平屋と2階建てのどちらを建てようか迷った場合にチェックすべきポイントをまとめました。家づくりを選択する際の着眼点は、主に以下の2つが挙げられます。
・家事動線やプライバシー保護などライフスタイルに関する面
・税金やメンテナンス費といったコスト面居住スペースがワンフロアにまとまる平屋では、家事動線の効率化を図れ、階段を昇り降りする負担もありません。一方、2階建ては、平屋に比べてプライベートな空間を確保しやすのが魅力です。
また、固定資産税は平屋で高くなりやすい傾向にあるものの、外装や屋根のメンテナンスは足場を組む必要がある2階建てのほうが、高額になるといわれています。
平屋と2階建て、どちらを選ぶか判断するためには、暮らしやすさやランニングコストなど、自身が何を重視したいか明確にすることが大切です。
>>参考コラム:平屋と二階建てならどっちを選ぶ?コストや利便性などを徹底比較!
固定資産税を抑えた家づくりならR+houseネットワークの工務店へ
 写真⑧三重県_シックな色合いの中に木目が目を引く外観 .jpg 457.81 KB
写真⑧三重県_シックな色合いの中に木目が目を引く外観 .jpg 457.81 KB固定資産税は、2階建てより平屋でより高くなる傾向があります。ただし、固定資産税は住まいの広さや設備などにより大きく異なるため、家づくりの工夫で賢く税額を抑えましょう。平屋と2階建てで迷った際は、建築費用だけでなく、ランニングコストや暮らしやすさなど、優先したいポイントの把握が大切です。
R+houseネットワークの工務店は、土地探しからお施主様をしっかりサポート。断熱性・気密性・耐震性に長けた理想の住まいを手の届く価格で実現できます。家づくりにお悩みの方は、ぜひお近くのR+houseネットワークの工務店までご相談ください。
>>R+houseネットワークなら暮らし始めてからも高いコストパフォーマンスを発揮!コストのしくみについてはこちら