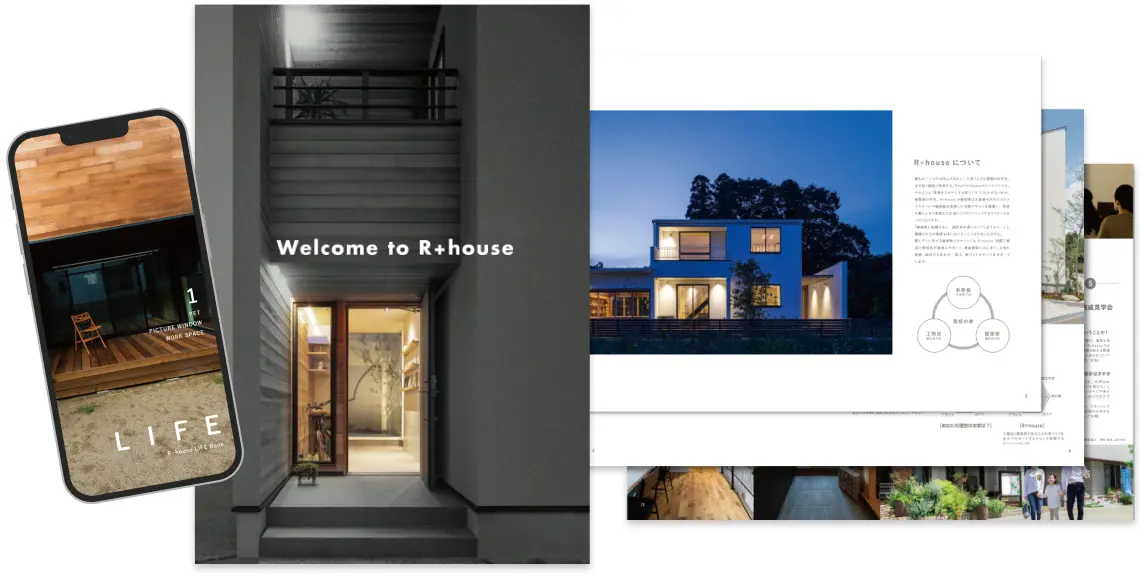長期優良住宅とは?次世代に継承できる良質な住宅
写真②茨城県_木目フローリングと大きな窓があるリビング.jpg 276.06 KB 長期優良住宅とは、長期にわたって良好な状態で住み続けられると国から認定された住宅を指します。 認定された住宅は、住宅を建てた世代はもちろん、次世代にも受け継いで住み続けることが可能です。長期優良住宅の特徴を以下にまとめました。
・長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備がある
・地震などの自然災害に強い
・省エネで環境に配慮されている
・将来次世代に引き継いで住み続けられる
長期優良住宅認定制度が始まった2009年には、共同住宅などを含む新築のみでしたが、2016年には増築・改築も対象に。2022年には、既存住宅も認定対象になりました。
参考元:国土交通省|長期優良住宅のページ
長期優良住宅の認定条件
新築一戸建てにおける長期優良住宅認定のチェック項目は以下の表の通りです。
性能項目等
目的
基準
劣化対策 住宅の構造躯体が数世代にわたって使用できる
・劣化対策等級(構造躯体等)3
耐震性 極めて稀に発生する地震に対して、損傷レベルを低減し継続利用できるよう、改修の容易化を図る
以下の条件例などに該当
省エネルギー性 必要な省エネルギー性能の確保
・断熱性能等級5
維持管理の容易性 構造躯体よりも耐用年数の短い設備配管の点検・清掃・補修・更新を容易にする
・維持管理対策等級(専用配管)3
居住環境 良好な景観の形成や地域の居住環境維持・向上に配慮する
・地区計画や景観計画、建築協定、景観協定、条例によるまちなみ等の計画等の内容と調和を図る
住戸面積 良好な居住水準を確保する
・75㎡以上
維持保全計画 将来を見据えた定期点検や補修などに関する計画を策定する
以下の部分や設備についての定期点検や補修に関する計画を策定
災害配慮 自然災害による被害防止や軽減に配慮する
・所管行政庁が定めた地域の災害発生リスクに応じた措置を講じる
そのほか、長屋や共同住宅の場合は、可変性や更新の容易性、バリアフリー性も項目に追加されます。
参考元:国土交通省|「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について 新築版
長期優良住宅認定の現状
国土交通省のデータをもとに、戸建て住宅における長期優良住宅認定実績の累計をまとめました。
新築
1,557,320件
増築・改修
1,702件
既存
94件
2023年までに認定を受けた新築戸建ての数は、155万件以上でした。 認定制度開始の2016年を除くと、毎年10万件以上の認定住宅が新築されており、長期優良住宅が年々普及していることがわかります。
参考元:国土交通省|長期優良住宅建築等計画の認定実績(令和6年3月末時点)
「長期優良住宅の普及に促進に関する法律」の背景
長期優良住宅認定制度は、2009年に制定された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づいて実施されています。
法律制定の背景として挙げられるのは、ストック重視の住宅政策への転換です。 長期優良住宅が普及すると、以下の3つの効果が見込まれます。
・環境負荷を低減する 「良いものをつくり、きちんとお手入れし、長く大切に使う」ことで解体や除却時に出る廃棄物の抑制に。また、建て替え費用がかからないため、国民負担の軽減も見込まれます。法律が制定された2009年においては、「現状よりも4倍程度長く住み続けることで、住宅建築や維持保全の費用を2/3ほどに縮減可能」と考えられています。さらに、建物自体の価値が長期にわたって維持できるため、国民資産の向上にもつながるでしょう。
参考元:国土交通省|長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針
長期優良住宅のメリット
写真③「メリット」と書かれた積み木.jpg 59.41 KB 長期優良住宅を建てるメリットを見ていきましょう。長期優良住宅のメリットには、以下の6つが挙げられます。
・減税や税制の控除 ・資産価値の向上 それぞれ詳しく見ていきましょう。
減税や税制の控除が受けられる
まず、メリットとして挙げられるのは、税制面での優遇です。長期優良住宅認定を受けることで対象となる税の特例措置を見ていきましょう。
所得税|住宅ローン減税の限度額引き上げ
所得税|投資型減税
登録免許税|税率の引き下げ
不動産取得税|控除額の増額
固定資産税|減税措置適用期間の延長
住宅ローンにおいて優遇される
長期優良住宅は、住宅ローンを組む際にも有利です。住宅ローンを借りる際に受けられる優遇をチェックしましょう。
フラット35S(金利Aプラン)・維持保全型
フラット50
地震保険料が割引になる
補助金対象になる
長く住み続けられる快適な家づくりが叶う
省エネルギー性の項目では、断熱等性能等級や一次エネルギー消費量等級に関する条件があります。
断熱性能の高い住宅は外気温による影響が少ないため、一年を通して室内を快適な温度の維持が可能に。ヒートショック予防や冷暖房費の節約にもつながるなど、快適で健康的に暮らせる家づくりが叶います。 また、長期優良住宅の条件には、劣化対策や耐震性の強化、維持保全計画によるメンテナンスなど、長きにわたって住宅を維持するための項目も揃っています。劣化に強く、快適な住宅に次世代まで住み続けられるでしょう。
参考元:国土交通省|「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について 新築版
資産価値が高くなる
「長期優良住宅認定を受けている住宅」は、資産性を高める材料となります。耐震や断熱など、高性能住宅であることが担保されていると、買い手も安心を得られるのが理由です。 そのため、長期優良住宅は、将来売却することになった際にも役立つでしょう。
長期優良住宅のデメリット
写真④「デメリット」と書かれた積み木.jpg 61.28 KB メリットが多くある長期優良住宅ですが、デメリットはあるのでしょうか?考えられる以下の3つのデメリットについて詳しく見ていきましょう。
・申請の費用や手間
申請の費用や手間
長期優良住宅認定を受けるには、申請費用が必要です。また、手続きの代行を依頼する場合、別途手数料がかかります。手数料は、代行を依頼する工務店やハウスメーカーによって異なりますが、書類作成費などを含めて20~30万円程度が目安です。 料金はかかりますが、手続きに不備がないよう代行を依頼するのが安心です。
建築費用増加や工期の長期化
維持費や定期的なメンテナンス
長期優良住宅は、認定時に策定した維持保全計画に従って、定期的なメンテナンスをする必要があります。
長期優良住宅における維持保全は、10年以内の間隔で30年以上続けるのが条件です。また、台風や地震の際には臨時点検を実施しなければなりません。 定期点検やメンテナンスができていないと判断されると、認定が取り消しとなる可能性もあります。忘れずに行いましょう。
R+houseでは注文住宅を建てるだけでなく、アフターサポートまで一貫して行っています。最低30年以上の長期メンテナンスプログラムの作成。定期点検を実施し、状況に応じたメンテナンスをご提案いたします。また、新築時や維持修繕の住宅履歴情報も管理しているため、長期優良住宅を希望する方にぴったりです。
参考元:国土交通省|「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の長期優良住宅認定制度の概要について 新築版
長期優良住宅の申請方法
写真⑤はてなマークと考えている表情の男女の若者のイラスト素材.jpg 84.06 KB ここからは、長期優良住宅の申請方法を説明します。スケジュールや必要書類を把握して、申請漏れのないよう注意しましょう。
長期優良住宅申請手続きのスケジュール
長期優良住宅の申請は、着工前から始める必要があります。ここでは、認定手続きの流れを着工前・着工後に分けてまとめました。
【着工前】
1. 長期優良住宅に対応している工務店を探す
【着工後】
長期優良住宅申請の必要書類・申請費用
長期優良住宅の申請時に必要な書類は以下の通りです。
【長期使用構造等であるかの確認】
・確認書/設計住宅性能評価申請書(長期使用構造等の確認結果記載のもの)
【所管行政庁への認定申請】
長期優良住宅を建てる際の3つの注意点
写真⑥ノートにクエスチョンマークと注意点の文字-min.jpg 65.31 KB 認定を受けることで税制面や補助金など、金銭面でのサポートが受けられる長期優良住宅。家づくりや手続きに失敗しないためにも、注意すべきポイントがあります。
長期優良住宅に長けている工務店選び
長期優良住宅を建てるには、条件をクリアした家になるよう設計を行わなければなりません。しかし、工務店やハウスメーカーなどによっては、長期優良住宅へ対応していないケースも。長期優良住宅を得意とする工務店を選択すれば、各チェック項目や申請手順を把握しているため、家づくりがスムーズに進められるでしょう。 また、わからないことがあった際に、気軽に相談できるのもポイントです。
申請手続きは工事着工前から
長期優良住宅の手続き開始は、着工前に行う必要があります。 せっかく条件をクリアした家づくりをしても「申請を忘れた」「漏れがあった」という場合は認定されません。認定制度の利用は、計画的に行う必要があるため注意しましょう。
予算オーバーに注意
長期優良住宅は、税制控除やローン金利の優遇など、金銭面でのサポートが受けられるのが魅力です。しかし、認定条件をクリアするために建築コストが比較的高くなる傾向があります。控除や優遇を受けたいからと、予算に見合わない住宅を建てるのは危険です。
予算をしっかりと把握し、見合わない場合は削れる部分を探しましょう。 R+houseでは、資金計画の重要性についてていねいに解説します。ライフプランシミュレーションで確認し、ローン返済計画だけでなく、教育費や生活コストなども細かく分析。借りられる額ではなく、返済できる計画をご提案しています。
>>参考コラム:注文住宅を建てるときに資金計画は必要?重要性と計画の立て方を解説
よくある9つの質問(FAQ)
写真⑦質問-min.jpg 83.6 KB 最後に、長期優良住宅に関するよくある質問を解説します。
Q1.長期優良住宅・ZEH住宅の違いは何ですか?
Q2.長期優良住宅のメンテナンスを放棄したらどうなりますか?
長期優良住宅認定を受けたにもかかわらずメンテナンスを放棄すると、所管行政庁より改善を求められます。改善指示に従わない場合は、長期優良住宅認定の取り消しとなります。
税の優遇措置や補助金を受けている場合、返還を要求される可能性もあるため、注意しましょう。 参考元:国土交通省|長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ
Q3.断熱等性能等級5以上の基準値は何ですか?
Q4.劣化対策等級3の基準とは何ですか?
劣化対策等級3は「住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上となるための必要な対策」と定められています。 1世代の目安を25~30年としているので、求められている耐久性は75~90年間以上です。
劣化対策等級を高めるためには、土台や外壁の軸組などにおける防腐・防蟻処理や浴室や脱衣室の防水対策などが求められます。とくにシロアリ対策に関しては、薬剤の有効期間が限られているため、建築時の防蟻処理だけではなく、定期的に対策を講じる必要があります。
つまり、正しいメンテナンスを続けていくことで、100年近く住み続けられる可能性があるのが長期優良住宅です。 参考元:国土交通省|3 劣化の軽減に関すること
Q5.長期優良住宅は途中でやめられますか?
Q6.「認定住宅」とはどのような意味ですか?
「認定住宅」とは、ある一定の基準をクリアしていると国に認められている住宅を指します。認定住宅には、長期優良住宅のほかにも認定低炭素住宅があります。認定低炭素住宅とは「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づいて低炭素建築物に該当する住宅です。
参考元:国税庁|認定住宅等とは
Q7.長期優良住宅は何坪からですか?
Q8.長期優良住宅取得率は何%ですか?
国土交通省のデータによると、新築戸建ての着工数に対して、長期優良住宅の認定率は2023年末時点で31.3%でした。 過去5年の新築戸建てにおける長期優良住宅認定実績と取得率は次の通りです。
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
認定戸数
107,393
100,503
118,490
115,509
111,262
認定取得率
24.9%
25.5%
27.8%
29.3%
31.3%
長期優良住宅認定戸数・取得率ともに増加傾向にあります。
参考元:国土交通省|長期優良住宅建築等計画の認定実績(令和6年3月末時点)
Q9.長期優良住宅認定が受けられないエリアはどこですか?
長期優良住宅認定を受けられない可能性があるのは、災害リスクの高いエリアです。 自然災害のリスクは地域によって異なるため、実情を踏まえて所管行政庁が基準を設定しています。土砂災害特別警戒区域などの災害リスクが非常に高い地域では、原則長期優良住宅認定されません。
また、土地区画整理事業による予想街路内等の区域内や優先整備路線の生活幹線道路の区域内などは、認定対象外となる場合があります。詳しくは、土地探しをする前に地域の所管行政庁へご確認ください。
R+houseは、土地探しからサポートいたします。長期優良住宅認定エリアであることはもちろん、耐震性に欠かせない地盤の強度や建ぺい率などの見えにくい注意点も考慮してより良い土地のご提案が可能です。
参考元:国土交通省|長期優良住宅認定基準の見直しに係る検討の方向性 参考元:練馬区|よくある質問と回答
長期優良住宅ならR+houseにお任せください!
写真⑧京都府_庭の植栽が美しい白と黒の家.jpg 283.21 KB 長期優良住宅の認定を受けるには、多くの条件をクリアする必要があります。申請に手間や費用がかかりますが、税制面や住宅ローン金利など、金銭面でのサポートが多い長期優良住宅。ほかにも、住みやすさや便利さ、安全面などさまざまなメリットがあります。長期優良住宅認定のメリットやデメリットを十分に理解して、計画的に家づくりを始めましょう。
R+houseでは、断熱性や耐震性などの性能を初めとする、長期優良住宅認定条件をクリアした家づくりを得意としています。耐震性は、許容応力度計算などを用いた構造計算した耐震等級3を推奨。木造住宅でありながら、災害時に活動拠点となる警察書や消防署と同等の耐震性確保が可能です。また、高断熱性能においては、基準値をクリアするだけでなく、長期にわたって性能の良い断熱材を採用しています。長期優良住宅を検討している方は、是非一度R+houseにご相談ください。
>>補助金を活用した家づくりや長期優良住宅の認定も叶う!「R+house」についてはこちら