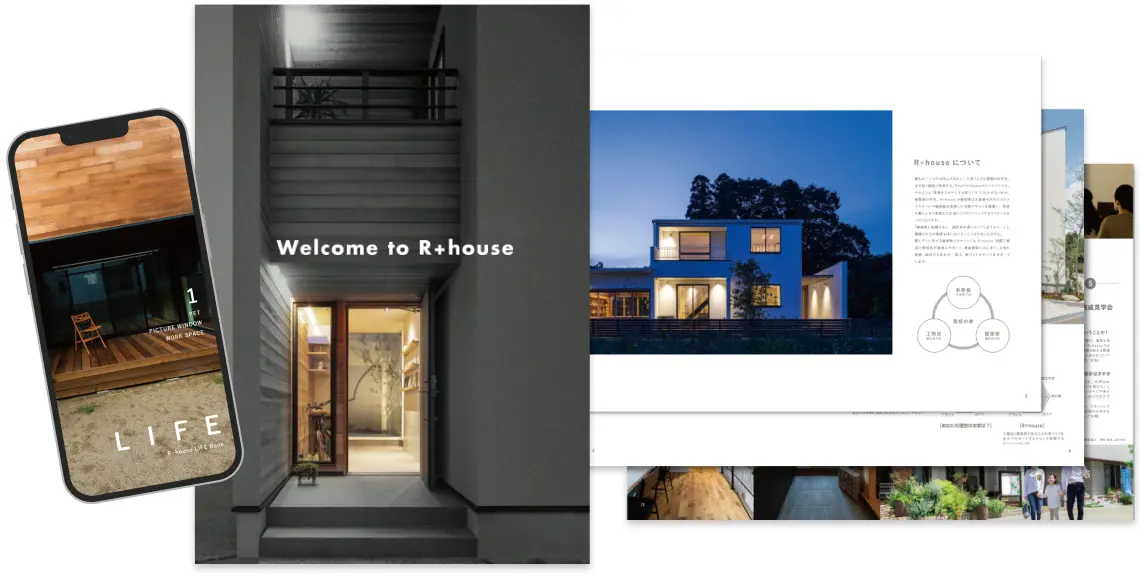在来工法とは?特徴や建築基準法の規定を解説
 写真②解説する人-min.jpg 85.63 KB
写真②解説する人-min.jpg 85.63 KB在来工法とはどのような建築方法なのでしょうか?在来工法の特徴や日本の木造住宅建築の歴史、建築基準法における定義などをわかりやすく解説します。
在来工法の種類や特徴
建築基準法における定義
建築基準法改正に伴う在来工法への影響
伝統構法・金物工法を徹底比較
 写真①木造軸組工法(在来工法)-min.jpg 91.93 KB
写真①木造軸組工法(在来工法)-min.jpg 91.93 KBここからは、伝統構法と金物工法について比較していきます。
|
伝統構法 |
金物工法 |
| 接合部 |
仕口・継手を用いた木組み |
金物によって固定 |
| 施工速度 |
遅い |
速い |
| 初期コスト |
比較的高い傾向がある |
伝統構法よりは抑えられる傾向にある |
| 耐震性 |
経年劣化によって耐震性低下のリスクがある |
地震や強風などへの耐性が比較的強い |
| 断熱性 |
比較できない |
比較できない |
| 空間設計 |
難しい |
しやすい |
| 見た目 |
デザインにより梁や柱などが露出するケースも |
接合部の補強金物は露出せずすっきりする |
| 木材消費量 |
多い |
少ない |
詳しく見ていきましょう。
接合部
伝統構法の接合部は、仕口と継手を用いた木組みをメインとしています。さまざまな種類の仕口・継手があり、芸術性があるのが魅力です。手作業で木材を加工する必要があり、熟練の技術を要します。
一方、金物工法の接合部固定に使用しているのは、金属製の部品です。金物で強固に連結して変形しにくくすることで、木材の動きを効果的に制限できます。伝統構法でも、接合部を釘や羽子板ボルトなどを用いて補強するケースもありますが、金属を使用して固定している金物工法に比べると強度が劣る傾向があります。
施工速度
金物工法は、伝統構法に比べて施工速度が速いのもメリットの一つです。木材の加工など現場で作業する工程が多いのが、伝統構法の工期が長引く理由です。また、仕口や継手を手作業でつくるため、職人の技量や天候によって施工期間に差が生じる可能性もあります。
その点、金物工法は、木材加工をあらかじめ工場で行うことが可能です。現場での施工プロセスが少ないため、伝統構法よりも工期が短くなります。
初期コスト
伝統構法は、木材のみを利用したシンプルな構造のため金属部材を揃える必要がありませんが、高度な技術を持つ職人が必要なため人件費が高くなります。また、建設期間が長引く傾向にあり、良質な無垢材や自然素材を使用することや、現代の建築基準法に適合させるための複雑な確認申請プロセスなどにより初期コストは高くなると考えられます。しかし、金物を使っていないので錆による劣化の心配がなく、建物を長持ちさせる構法です。数百年から千年以上にわたって日本の多くの神社仏閣が現存しているのもこの構法の影響が大きいといえます。
一方、金物工法の場合、木材に加えて金属部材を揃える必要があるため、その分の部材費や構造計算などのコストが発生しますが、プレカットによる工期短縮と現場での人件費削減、施工品質の安定化により、全体として伝統構法よりも初期費用を抑える傾向にあります。
耐震性
伝統構法は、木材の柔軟性によって地震の揺れを分散させる免震的・制震的な構造です。地震の揺れなどの外力を受けた際は、木がしなったり、曲がったりすることで力を逃します。
金物工法は、木材の柔軟性に接合部に用いた金属の変形しにくさを組み合わせることで耐震性を高めています。地震が発生した際は、木材の柔軟性によって揺れを効果的に分散。さらに、金属の接合部が木材同士の動きを制限してくれます。
しかし、どちらか一方が耐震性に優れている、ということはありません。耐震性はどの工法であっても構造計算などによって十分に高めることができます。
断熱性
構法による断熱性の違いは比較することはできません。しかし、金物工法を用いる場合に注意したいのが、ヒートブリッジ(熱橋)です。ヒートブリッジとは、局所的に熱移動が行われやすい部分を指します。金物工法では、木に比べて熱伝導率の高い金属部分から熱が移動しやすくなるため、断熱性が劣る可能性があります。
そこで、金属の接合部分の上から吹き付けウレタンフォームを施して熱移動が行われにくくなるよう処理をしたり、木材内部に組み込んで金物が露出しない状態に施工したりと工夫が必要です。ヒートブリッジを防ぐことで、建物の断熱性能をアップ。冷暖房が効きやすくなるため、光熱費の節約につながります。
伝統構法は、床下や天井裏に隙間ができやすい建て方です。伝統構法を採用する場合は、しっかりと気密施工を施し、高性能の外断熱材を活用するのがおすすめです。
空間設計
伝統構法を用いた場合、建物の耐震性を高めるためには、柱や壁を増やす必要があります。耐震性を確保するために増やした柱によって、理想の間取りにできないケースも少なくありません。しかし、伝統構法でも、お寺や神社に大きな空間があるように、大断面の梁を使えば大空間を作ることは可能です。
金物工法では、接合部に特殊な金物を使用することで木材の断面欠損を最小限に抑え、柱や壁の数を減らした設計が可能になります。開放感のあるLDKや吹き抜けのある住宅づくりにも適しています。
見た目
建築方法の違いは、見た目にも影響を与えます。金物工法の場合、金属部分が外側に見えることはほとんどありません。すっきりとした見た目なので、化粧梁など住宅のデザインとして活用するのにも適しています。
伝統構法は、美しく芸術的な木組みが特徴です。しかし、手作業で行うため、職人の技術力によって仕上がりが左右されるかもしれません。
木材消費量
木材を削る必要がある伝統構法は、その分廃材の量も多くなります。また、構造を支えるためには、大量の木材が必要です。そのため、伝統構法は木材消費量の多い建築方法といわれています。
一方、金物工法は廃材が少ない傾向があります。使用される木材は標準化されており、工場でムダが少なくなるよう加工されているのが理由です。また、金物に関しても、再利用可能なため、廃棄物にはなりません。金物工法は、資源消費が少ないため、環境への負荷が少ないといえるでしょう。
木造住宅の建築方法「ツーバイフォー(2×4)工法」とは?
 写真④家の疑問-min.jpg 62.65 KB
写真④家の疑問-min.jpg 62.65 KB木造住宅を建てる際の建築方法として、軸組工法とよく比較されるのがツーバイフォー工法です。
ツーバイフォーとは、「木造壁式構法」や「枠組壁工法」とも呼ばれ、建物を壁で支えるのが特徴です。四方の壁と天井、床の合計6面のパネルを構造体としています。枠組みをつくる際に使用する木材の主な断面のサイズである2×4インチが、ツーバイフォーの由来です。とはいえ、場所によっては、2×6や2×8といった別サイズの木材を使用することもあります。
>>参考コラム:木造建築は新築住宅に向いている?メリット・デメリットを徹底解説
在来工法・ツーバイフォー工法を徹底比較
 写真⑤家を比較する女性-min.jpg 55.33 KB
写真⑤家を比較する女性-min.jpg 55.33 KBツーバイフォー工法は、在来工法とどのような違いがあるのでしょうか?在来工法は、木造軸組工法の一種であるため、ツーバイフォー工法と木造軸組工法(以下、軸組工法)を比較して解説していきます。
|
軸組工法 |
ツーバイフォー工法 |
| 耐力要素 |
柱・梁・床・壁・天井/屋根・筋かい |
柱・梁・床・壁・天井/屋根 |
|
| コスト |
比較的低い |
比較的高い |
| 間取り |
自由度が高い |
比較的自由度が低い |
| 開口部 |
大きくとれる |
制限がある |
| 可変性 |
大規模なリノベーションや間取りの変更がしやすい |
大規模なリノベーションは難しい |
| 見た目 |
自由度が高い |
凹凸が少なく、シンプルな形状 |
| 品質 |
職人によって左右される |
一定に保ちやすい |
| 耐震性 |
構造計算結果次第 |
構造計算をしない場合でも比較的高い強度を保てる |
| 気密性 |
気密施工次第 |
確保しやすい |
| 耐火性 |
変わらない |
変わらない |
具体的に見ていきましょう。
耐力要素
軸組工法の耐力要素は、柱・梁・床・壁・天井/屋根・筋かいです。柱や梁でつくられた枠の中に、筋かいを斜めに渡すことで強度を保っています。軸組工法で住宅を建てる場合、地震や強風による建物の変形を防ぐために筋かいが用いられることが多いです。
一方、ツーバイフォー工法の場合は、面で建物を支えているため、筋かいは入れません。4面の壁と天井、床のボックス型の構造になっているため、筋かいを入れなくても横からの振動に強くなっています。
コスト
ツーバイフォー工法の方が軸組工法よりやや割高になります。ツーバイフォー工法が普及している北海道などを除き、多くの地域で軸組工法が主流のため材料の価格も抑えられ、職人の数も多いので軸組工法の方が比較的安くなります。ツーバイフォー工法は、大手ハウスメーカーが採用していることもあり、コストとしては高くなります。
R+houseは、コストパフォーマンスにも自信があります。建築家とつくるこだわりのマイホームを実現するために、材料費や現場管理費、営業経費を抑える努力を行っています。「予算内で理想の注文住宅を建てたい」とお考えの方はぜひ一度R+houseにご相談ください。
>>参考コラム:注文住宅の相場はどのくらい?費用の内訳や予算計画を立てる際のポイントも!
間取り
軸組工法は、間取りの自由度が高いのがメリットです。建物を柱や梁で支えているため、壁の配置に制限が少なくなります。広々とした空間づくりや天井の高さの確保も可能です。
ツーバイフォー工法を採用した場合、建物を支える構造躯体が壁になります。構造の強度を保つために、建物を支えている耐力壁は削れません。また、1階と2階の耐力壁は、同じ位置にするよう設計します。結果、間取り決めの際に制約が生まれます。
開口部
間取り同様、開口部にも制限があるのがツーバイフォー工法です。規格内に収めることや、建物の強度の観点から見ても、開口部の広さには限界があります。
一方、軸組工法は、開口部を大きくとることが可能です。広さだけでなく、開口部の数や種類も比較的自由に計画できます。
可変性
リフォームやリノベーションといった住宅の可変性は、ツーバイフォー工法の方が難しいと言えます。新築時の間取り決め同様、壁量の確保が必要だからです。一方、軸組工法は制約が少ないのがメリットです。
ただ、軸組工法を用いて住宅づくりをしたとしても、強度を保つためにリフォームやリノベーションの制約はゼロではありません。しかし、ツーバイフォー工法と比較した場合、軸組工法のほうが大規模なリノベーションや間取りの変更に適しているといえます。
見た目
一概に外観のみで判断できるわけではありませんが、軸組工法とツーバイフォー工法とでは、見た目にも特徴が表れます。ツーバイフォー工法を用いて建てられた住宅は、凹凸のないシンプルな形状が一般的です。6面を基本構造としているため、箱を積み重ねたような仕上がりになります。1階と2階の壁が同じ位置にないなど、個性的な見た目の住宅は在来工法の可能性が高いでしょう。
品質
仕上がりの品質に差が出にくいのは、ツーバイフォー工法のメリットです。現場での資材加工がなく、使用部品や手順が細かく定められているため、品質が職人の腕に左右されることがありません。しかし、工場での管理方法や生産過程によって品質が変わるため、住宅会社の選択は慎重に行いましょう。
耐震性
「ツーバイフォー工法の建物のほうが在来工法に比べて強度は高い」といわれることがあります。
しかし、在来工法(軸組工法)の耐震性が劣っているとは一概にはいえません。軸組工法は柱や耐力壁のバランス、筋かいの配置や向きなどによって、耐震性を高めることが可能です。R+houseでは、許容応力度計算などの構造計算を活用することで、高い耐震性を目指せます。
>>参考コラム:耐震とは?快適な暮らしに必要な耐震の知識|メリット・デメリットも解説
気密性
ツーバイフォー工法は、比較的気密性に優れています
。面を組み合わせて住宅を建てるため、隙間ができにくいのが理由です。一方、軸組工法は、隙間ができやすいのが弱点です。パッと見ただけではわからない隙間でも、外気が入り込んでしまうため、断熱性にも影響します。
そのため、軸組工法では、気密性を高めるために、気密テープや断熱材を活用して、隙間を塞ぐ工夫が必要です。在来工法を採用している住宅会社には、気密性を表すC値を提示しているケースがあります。「在来工法が良いけれど気密性が気になる」という方は、ぜひC値をチェックしてみてください。
現在、気密性の明確な基準はありませんが、一般的に寒冷地ではC値2.0、それ以外では5.0以下が必要といわれています。しかし、C値は経年劣化によって大きくなる可能性も。長期に渡って快適に過ごせるよう、R+houseでは新築時、平均C値を0.5程度と高い気密性を実現しています。
>>参考コラム:注文住宅を高断熱・高気密にするメリットとは?快適な家づくりを徹底解説!
防火性
ツーバイフォー工法は、防火性を確保しやすい構造です。面が多いため、炎を跳ね返しやすいのが理由です。在来工法では、防火性を高める工夫を行う必要があります。ツーバイフォー工法を応用したファイヤーストップ材などを活用することで、軸組工法の防火性を高められます。
こだわりの家づくりならR+houseネットワークの工務店へお任せください
 写真⑥熊本県_2階の大きな窓が印象的な白い外観の家.jpg 245.72 KB
写真⑥熊本県_2階の大きな窓が印象的な白い外観の家.jpg 245.72 KB日本で古くより用いられてきた、柱と梁によって住宅を支えているのが在来工法です。この記事では、在来工法(木造軸組工法)を中心に、その特徴、伝統構法や金物工法といった種類、さらにツーバイフォー工法との比較を通じて、それぞれの建築方法のメリット・デメリットを解説しました。建築方法によって、叶うことや難しいことが異なります。「間取りにこだわりたい」「予算を抑えたい」など、理想を叶えるためには、希望に合った住宅の建築方法を選ぶのが大切です。メリット・デメリットを十分に理解して、理想のマイホームを目指しましょう。
R+houseネットワークの工務店は、建築家と連携して進める家づくりが特徴です。建築家ならではの高いデザイン性と、優れた断熱・気密・耐震性能を備えた住まいが建てられます。さらに、部材の標準化といった独自のルールにより、高性能なデザイン住宅を手の届く価格で提供できるのも強みです。北海道から沖縄まで全国各地にR+houseネットワークに加盟している工務店があり、あなたの家づくりをサポートしますので、注文住宅づくりを検討している方は、ぜひ一度お近くのR+houseネットワークの工務店へご相談ください。
>>建築家と建てる家づくりでこだわりのマイホームを!「R+house」についてはこちら