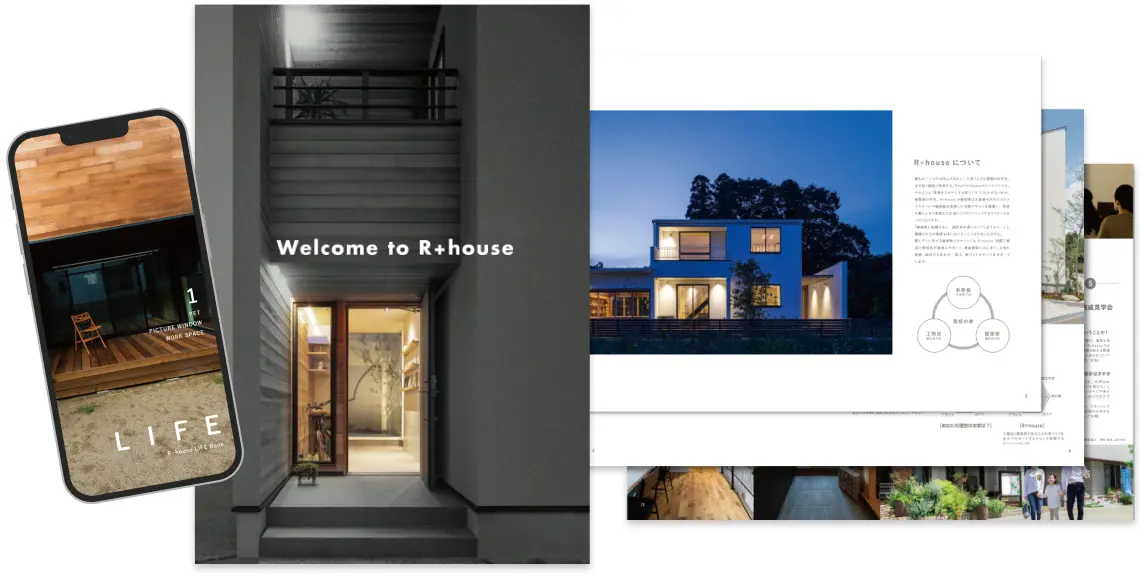住宅ローン6,000万円を組む前に!住宅以外の費用についても知っておこう
 住宅ローン (1).jpg 71.72 KB
住宅ローン (1).jpg 71.72 KB6,000万円の住宅ローンを組む場合、住宅にかけられる費用がどのくらいなのかをご存知ですか。マイホーム購入時に必要なのは、建築費だけではありません。そのほかに必要となる土地取得費や諸費用についてまとめました。
土地取得費
諸費用
注文住宅の諸費用には、建築請負契約の印紙税・登記費用のほか、住宅ローンの融資手数料・保証料、保険料などが含まれます。
諸費用の目安は、土地と建物を合計した金額の10~12%程度です。例えば、土地と建物を合わせた金額が5,000万円なら500~600万円程度、6,000万円なら600~720万円程度の諸費用が必要となります。
このように、住宅ローンを6,000万円で組む場合は、建築費だけでなく、土地取得費や諸費用もかかることを知っておきましょう。
>>参考コラム:注文住宅の購入には諸費用がかかる!項目や費用の目安を知っておこう
6,000万円の住宅ローンで考えたい!返済負担や家計とのバランス
 写真③住宅と資金の象徴的バランス-min.jpg 85.23 KB
写真③住宅と資金の象徴的バランス-min.jpg 85.23 KB住宅ローンを組むときは、家計とのバランスを考慮する必要があります。ここでは、目安となる年収倍率や返済負担率、共働きの場合に利用できる可能性のある仕組みなどをご紹介します。
年収倍率から考える住宅ローン
年収倍率とは、住宅の購入にかかる金額を世帯年収で割って算出したもの。新築住宅なら、6~8倍を目安にしましょう。
ただし、マイホーム購入費用=住宅ローン借入額ではない点には注意が必要です。頭金を用意するのが一般的なため、実際の住宅ローンの借入額は、年収の5~6倍程度にとどめましょう。単純計算では、年収1,000~1,200万円で6,000万円を借り入れることになります。
返済負担率から考える住宅ローン
返済負担率(返済比率)は、年収に占める年間返済額の割合のこと。金融機関では、返済可能な計画であるかを判断する材料として、この返済比率を確認しています。
昨今の資材高を考えると、返済負担率は30%程度に設定するのがおすすめです。例えば、年収800万円なら月20万円程度、年収1,000万円なら30万円程度が目安となるでしょう。
【共働き夫婦必見】住宅ローンの借り方の選択肢と特徴は?
共働きの場合は、単独ローン・ペアローン・収入合算という3種類の借り方があります。それぞれの特徴についてご説明します。
単独ローン
最も一般的なのが、夫婦のどちらか片方が借り入れる単独ローンです。特徴は以下を参考にしてください。
| メリット |
デメリット |
・諸費用が1人分で済む
・産休などの収入減少リスクが1人分で済む
・離婚や相続などの際にトラブルになりにくい |
・借入可能額が1人分の収入により決まるため増やしにくい
・住宅ローン控除は1人分しか受けられない
・住宅ローン審査が厳しい傾向にある |
手続きがシンプルで、収入が減少した際のリスクを小さく抑えられる点が特徴です。一方で、ほかの方法に比べると、借入可能額が少ないというデメリットがあります。
ペアローン
夫婦それぞれが主債務者となり2本分の住宅ローンを組むことを、ペアローンといいます。特徴を表にまとめました。
| メリット |
デメリット |
・単独ローンより借入可能額を増やしやすい
・早期返済の計画を立てやすい
・2人とも住宅ローン控除を受けられる
・2人とも団信(※)に加入できる |
・2人分の諸費用が必要
・収入減少の際のリスクが2人分になる
・借入金額を多く見積もった結果、家計の負担が大きくなることも
・離婚時の住宅ローンの扱いが難しい |
※返済中の万が一にそなえる団体信用生命保険でのことで、死亡などの際にローン残高がゼロになる。
ペアローンは、単独ローンより多く借りられるのが魅力です。2人ともが住宅ローンの控除を受けられる点も特徴といえるでしょう。一方で、諸費用が2人分必要になったり、離婚した際の扱いが難しかったりする点は、デメリットです。
収入合算
収入合算は、ローンの主債務者は1人のまま、夫婦の収入を合算して借入額を増やす方法。夫婦間で収入の差がある場合は、収入合算を選ぶのがおすすめです。基本的には、収入が多い方が主債務者、そして少ない方が連帯保証人になります。特徴を詳しく見ていきましょう。
| メリット |
デメリット |
・2人分の収入を合算できるため、借入可能額を増やせる
・1人分の諸費用で済む |
・主債務者が返済できなくなった場合は、連帯保証人が返済義務を負う
・主債務者しか団信に加入できない
・住宅ローン控除を受けられるのが主債務者のみ |
収入合算の特徴は、諸費用は1人分のままで、借入可能額を増やせること。しかし、主債務者しか団信に加入できないため、連帯保証人に何かあったとしてもローン残高はゼロになりません。こういったケースにそなえて、別の生命保険に加入するなどの選択肢を検討すると良いでしょう。
住宅ローンで6,000万円を借り入れる場合の返済シミュレーション
 写真④住宅模型と電卓-min .jpg 85.63 KB
写真④住宅模型と電卓-min .jpg 85.63 KBここからは、6,000万円の住宅ローンを組む場合の返済額を、さまざまなパターンでシミュレーションします。※融資手数料・保証料を0円として計算しています。
返済方法で比較!35年ローンだと毎月の返済額はいくら?
住宅ローンの返済方法には、元利均等返済と元金均等返済があります。元利均等返済とは、毎月一定の返済額を支払う方法のこと。そして元金均等返済とは、毎月支払う返済額のうち、元金が一定になる返済方法です。
返済期間を35年として、同じ条件で返済額を比べてみましょう。全期間固定金利(年2.0%)、ボーナス払いなしで計算しました。
元利均等返済の場合
6,000万円の住宅ローンで元利均等返済を選んだ場合の毎月返済額は、以下の通りです。
| 毎月返済額 |
約19.9万円 |
| 総返済額 |
約8,347.8万円 |
元利均等返済は毎月の金額が固定されるため、返済計画を立てやすいことがメリットです。また、元金均等返済よりも、返済開始当初の返済額が少なく済む点も魅力といえます。一方で、返済期間が同じ場合は、総返済額が高くなるというデメリットもあります。
元金均等返済の場合
今度は、同じ条件で返済方法のみを元金均等返済に変えて試算しました。
| 毎月返済額 |
1ヶ月目:約24.3万円
10年1ヶ月目:約21.7万円
20年1ヶ月目:約18.9万円
30年1ヶ月目:約16.0万円
35年1ヶ月目:約14.6万円 |
| 総返済額 |
約8,105.0万円 |
元金均等返済は、返済開始当初の支払い負担は大きいですが、返済が進むにつれて毎月返済額が減っていくのが特徴です。元利均等返済よりも元金が早く減るため、期間が同じなら総返済額は少なくなるでしょう。実際、今回のシミュレーションでも、総返済額に約242.8万円の違いがあります。
金利タイプで比較!35年ローンだと毎月の返済額はいくら?
金利タイプは、全期間固定金利のほかに、変動金利や固定金利期間選択型などもあります。ここでは返済方法を元利均等返済として、変動金利(年0.8%)で試算し、前述の全期間固定金利と比べてみましょう。※ボーナス払いなしで試算しています。
| 毎月返済額 |
約16.4万円 |
| 総返済額 |
約6,881.1万円 |
変動金利は、固定金利と比べて金利が低いことがメリット。同じ元利均等返済で比較すると、総返済額は全期間固定金利より約1,466.7万円安くなっています。ただし、ここで算出した毎月返済額は金利が年0.8%の場合のものであり、あくまでも目安です。実際には金利が市場金利に伴って変動するため、当初の予定とは異なった金額になる可能性はあるでしょう。
なお、固定金利期間選択型は、期間終了後の金利タイプの選び方次第で毎月返済額や総返済額が変わります。今回はシミュレーションしていませんが、金融機関のウェブサイトでは条件を細かく設定して試算可能です。
>>参考コラム:【保存版】住宅ローン完全攻略ガイド!金利タイプやシミュレーションも
共働きの借り方で比較!年収・世帯年収別の毎月の返済額はいくら?
次に、共働きのケースで試算してみましょう。ボーナスの併用や返済期間の短縮といった返済プランもシミュレーションに含めているので、余裕があれば検討してみてください。
【単独ローン】年収1,200万円でボーナス払いあり・30年の場合
6,000万円を単独ローンで、1,500万円分をボーナス払いに設定して返済期間を30年に短縮すると、毎月返済額・総返済額はどのように変わるでしょうか。※変動金利(年0.8%)、元利均等返済とします。
| 毎月返済額 |
約14.1万円 |
| 総返済額 |
約6,753.2万円 |
【収入合算】世帯年収1,500万円(夫1,200万円・妻300万円)・20年の場合
夫婦の年収を合算し、世帯年収1,500万円で返済期間を20年に短縮するケースの試算結果は、以下の通りです。※変動金利(年0.8%)、元利均等返済とします。
| 毎月返済額 |
約27.1万円 |
| 総返済額 |
約6,494.8万円 |
世帯年収1,500万円、毎月返済額約27.1万円の場合の返済負担率は21.7%。無理のないプランといえます。
このように、収入合算すれば、返済期間を20年に短縮するなど、さまざまな返済の仕方が可能です。
【ペアローン】世帯年収1,500万円(夫800万円・妻700万円)・25年の場合
返済期間を25年として、夫3,500万円、妻2,500万円でペアローンを組むケースを想定してみましょう。※変動金利(年0.8%)、元利均等返済とします。
|
夫 |
妻 |
合計 |
| 毎月返済額 |
約12.9万円 |
約9.2万円 |
22.1万円 |
| 総返済額 |
約3,862.8万円 |
約2,759.1万円 |
6,621.9万円 |
6,000万円の住宅ローンで後悔しないためには
シミュレーション結果からも分かるように、住宅ローンは、返済方法・金利タイプによって毎月返済額・総返済額が大きく変わります。
総返済額を抑えるためには、ボーナス払いや返済期間の短縮も視野に入れて試算してみましょう。共働き夫婦は、収入合算やペアローンといった選択肢も出てきます。後悔のないように、さまざまなパターンで検討してプランを立てましょう。R+houseは、安心して家づくりをしていただけるように、資金計画のサポートも行っています。住宅ローン以外の相談も可能ですので、ぜひお声がけください。
>>参考コラム:注文住宅を建てるときに資金計画は必要?重要性と計画の立て方を解説
契約後に総返済額を抑えたい!知っておくべき借り換え・繰り上げ返済とは
 写真⑤家と財布と家族.jpg 87.35 KB
写真⑤家と財布と家族.jpg 87.35 KB
総返済額を抑えたいときは、借り換えや繰り上げ返済なども有効です。それぞれの特徴と注意点をまとめました。
【借り換え】
・金利の低いローンに借り換える方法
・借り換えの諸費用も含めて検討しよう
【繰り上げ返済】
・資金に余裕ができたときに繰り上げて返済する方法
・当初の予定より利息負担を減らせる
・金融機関により手数料や繰り上げ返済可能額が異なるため確認が必要優先順位としては、借り換えの検討が先となります。各金融機関のウェブサイトで金利をこまめにチェックし、低く借りられるところがあれば試算してみましょう。
次に考えるのが繰り上げ返済です。貯蓄分とのバランスも考えて、余裕資金があればこまめに繰り上げ返済をしましょう。
>>参考コラム:金利上昇に備えるために…住宅ローンの組み方はこう考える!
マイホームや住宅ローンのご相談はR+houseネットワークの工務店へ!
 写真⑥愛知県_L字に窓がある白い外壁の家 .jpg 86.72 KB
写真⑥愛知県_L字に窓がある白い外壁の家 .jpg 86.72 KB同じ6,000万円の住宅ローンでも、返済方法や金利タイプなどにより、返済額が異なることが分かりました。住宅ローンで後悔を避けるためには、多くのパターンを想定し、試算してみることが重要です。
R+houseネットワークの工務店が手がける注文住宅は、建築家による個性を活かしたデザインや快適に暮らせる性能、無理・無駄のないコストが特徴です。R+houseネットワークの工務店は、全国に210店舗以上あります。モデルハウス見学会や個別相談会なども行っていますので、ぜひR+houseネットワークの工務店までお声がけください。
>>後悔のない理想のマイホームを手に入れよう!R+houseネットワークのコストのしくみについてはこちら